社会学部ゼミブログ

2017.09.28
- 社会学部
- 社会学科
ダンスで社会学!?—ゼミを通して学ぶ質的調査方法
ブログ投稿者:社会学科 准教授 林 玲美(リム ヨンミ)

2年次必修科目の一つである社会調査実習では、ゼミごとにテーマを設定し、実際に調査に取り組むことを通して社会調査のさまざまな方法を学んでいきます。大きく分けて、量的社会調査(実習では主にアンケート調査を実施し収集したデータを統計的に分析しつつ仮説を検証していくもの)に取り組むゼミや、質的社会調査(参与観察や聞き取り調査にもとづいてさまざまな社会事象を探索的に理解していこうとするもの)に取り組むゼミがありますが、私が担当しているゼミは、ダンスと現代日本社会の関わりについて質的社会調査を進めています。
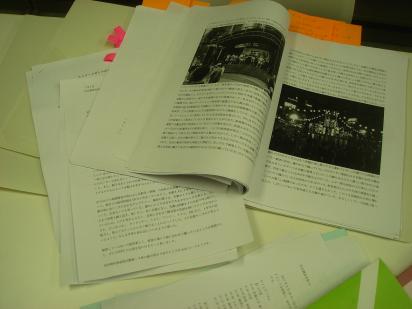
「え?ダンス!?」と思われるかもしれませんが、社会学では人間社会に関わるあらゆる事象が調査の対象になります。肉眼の観察では認識できないことを、何らかの「見える」かたちにしていきながら、系統だったやり方で整理し、分析を進めつつ概念どうしの関係を解き明かしていきます。いろいろなダンス現象を追うことで見えてくる、現代日本社会の興味深い「何か」を一年間かけて解明していきます。

週に一度集まる教室内での活動と、実地調査のプロジェクトをデータの収集・分析・報告書の執筆まで年度内にすべて完成するため、教室の外で行う調査・分析・執筆に関わる活動があります。学期はじめには、質的社会調査方法の教科書やフィールド調査の理論や実践に関わる文献講読から入り、回を追うにつれ、ダンスに関連した先行研究を読み込み、テーマを絞っていく作業に入りました。担当する先行研究の文献をもとに発表をし、その内容や方法論について議論を進めつつ、フィールド調査も断続的に行いました。

身近なダンス現象ということで、とりかかりとして学内ストリートダンス・サークルの活動も参与観察することができれば、と考えていたところに、サークルの内部者が複数ゼミの中にいるというのは渡りに船です。学内サークルの練習の記録も部員であるゼミ生と、部員ではないゼミ生双方によって、スケジュールの許す範囲でフィールド・ノートが蓄積されていきました。キャンパス外のフィールド調査も、たとえば各地でショーケースなどのダンス・イベントもかなりの頻度で行われており、そうしたイベントに参加したゼミ生はそれぞれフィールド・ノートをその都度持ち寄ります。

7月にはゼミ全体で、としま未来文化財団・豊島区立舞台芸術交流センター『あうるすぽっと』主催の第10回近藤良平・コンドルズ『にゅ~盆踊り大会』に参加しました。その前に行われた盆踊りリーダー「しゃ~隊」養成ワークショップにも合わせて参加しました。ユーモラスかつシュールな振り付けの創作盆踊りを一緒に踊ることで、多様な人々が場を共有し、盛り上がるという熱気を体験し、思い思いのフィールド・ノートを作成しました。
さらに、夏休み中には、ひとりひとりが、身近なダンス・イベントに参加し、参与観察に挑戦しました。
後期は、ゲスト・スピーカーを迎えたり、ゼミ生が個別にインタビュー調査を行う実習を行います。また、各自のテーマに沿ったフィールド調査の、データ分析作業が始まります。生身の人間が織りなす日常生活の中にある豊かな営みや、人間と社会の重層的な関わりを、単純に図式化しすぎないようにと思いつつ、個性豊かなゼミ生たちとの活動を毎週とても楽しみにしています。
