学部横断ゼミブログ

2025.05.02
資料を集める
ブログ投稿者:学部横断型課題解決プロジェクト運営チーム 伊藤 普子
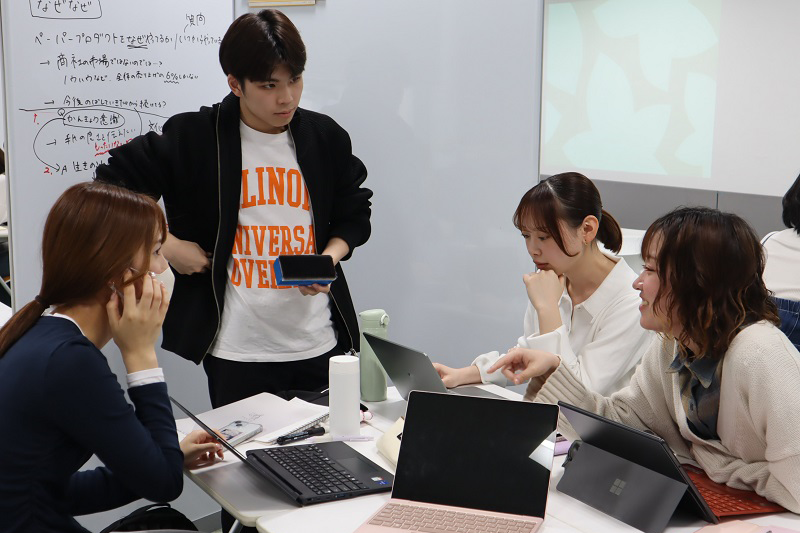
4月28日(月)の2時限目に授業が行われました。GWに入る関係で、5月12日(月)に行われる中間発表会のプレプレ発表前の最後の授業となりました。4月から調べ始めた段階であることを考えると、残り2週間で発表の内容をまとめなければならないということは、かなりタイトなスケジュールです。

授業の冒頭で教員からは、「群盲象評」の例えを使いながら広く深く情報を集めるようにとアドバイスがありました。また、今回は授業後に昨年度秋学期の履修生に、収集した情報をチームでどのように整理し可視化したのかレクチャーしてもらいました。
先輩が語ってくれたように、根気よく情報を集め、それを丁寧に考察することが良い発表に繋がります。中間発表会に向けて焦るばかり、どのチームも情報収集が足りないまま分析をはじめてしまっています。今回の授業でも、チームでの話し合いが堂々巡りになってしまう場面があり、まだまだ調べなければいけないことがたくさんあることに気づいたようです。
情報を丁寧に集め、今回の課題提供企業である㈱竹尾を<きちんと知る>努力を惜しまないでほしいと思います。
先輩が語ってくれたように、根気よく情報を集め、それを丁寧に考察することが良い発表に繋がります。中間発表会に向けて焦るばかり、どのチームも情報収集が足りないまま分析をはじめてしまっています。今回の授業でも、チームでの話し合いが堂々巡りになってしまう場面があり、まだまだ調べなければいけないことがたくさんあることに気づいたようです。
情報を丁寧に集め、今回の課題提供企業である㈱竹尾を<きちんと知る>努力を惜しまないでほしいと思います。

学部ごとに分かれたチーム活動も、3週間が過ぎました。学年・学科のみならず、性格や価値観が違うメンバーとの活動は、自分の短所ばかりに目が行き、自信をなくすこともあるようです。一方で、自分の役割を探して主体的に活動するプロセスの中で、着実に成長を感じさせる履修生もいます。
この授業の目的の一つに、「社会人基礎力の育成」があります。故意に目の前の課題から目を背けるのではなく、自己成長のために失敗を恐れずに意欲的に活動してみてください。
この授業の目的の一つに、「社会人基礎力の育成」があります。故意に目の前の課題から目を背けるのではなく、自己成長のために失敗を恐れずに意欲的に活動してみてください。
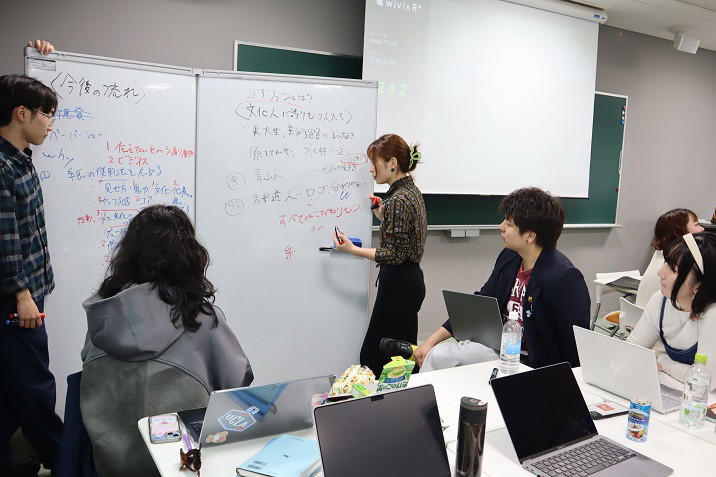
最後に、授業後の学生の日記を紹介します。
「今回の授業では、まず先生の「群盲象を評す」の話から始まった。この話を私は初めて聞いたが、今の自分たちがまさしくこの寓話の状況だなと思った。今までの私達は経営理念を一つの軸にして竹尾を見ていたが、情報収集が足りておらず竹尾をちゃんと見れていなかったなと思った。また、今回の授業では発表のアウトラインを決めるという予定であったが、軸を決めるのまだ早いという指摘をいただいた。軸を決めてしまうとその軸に偏ってしまうという指摘にはっとした。私は先に軸を決めることでスムーズに進めることができると思っていたため軸を先に決めるべきだと思っていたが、決めた軸に縛られてしまい偏ってしまっていたなと思った。
先生の話の後、チームでの活動を始めた。<why>を繰り返して考える方法を使い、先生のお話にあった氷山のお話でいう<invisible>を考えていった。最初のほうはどんどん意見が出ていたが、深くなるごとに議論が捗らなくなっていってしまった。これは情報量の少なさに原因があると思うのでチーム内でもっと情報を集めることにした。」
「今回の授業では、まず先生の「群盲象を評す」の話から始まった。この話を私は初めて聞いたが、今の自分たちがまさしくこの寓話の状況だなと思った。今までの私達は経営理念を一つの軸にして竹尾を見ていたが、情報収集が足りておらず竹尾をちゃんと見れていなかったなと思った。また、今回の授業では発表のアウトラインを決めるという予定であったが、軸を決めるのまだ早いという指摘をいただいた。軸を決めてしまうとその軸に偏ってしまうという指摘にはっとした。私は先に軸を決めることでスムーズに進めることができると思っていたため軸を先に決めるべきだと思っていたが、決めた軸に縛られてしまい偏ってしまっていたなと思った。
先生の話の後、チームでの活動を始めた。<why>を繰り返して考える方法を使い、先生のお話にあった氷山のお話でいう<invisible>を考えていった。最初のほうはどんどん意見が出ていたが、深くなるごとに議論が捗らなくなっていってしまった。これは情報量の少なさに原因があると思うのでチーム内でもっと情報を集めることにした。」
