学部横断ゼミブログ

2021.06.09
『CSR報告書』作成のための話し合い
ブログ投稿者:学部横断型課題解決プロジェクト運営チーム 伊藤 普子

6月7日(月)の2時限目に授業が行われました。2チームともに1時限目から集まり、活発な意見交換が行われていました。
授業では、まず2チームそれぞれの進捗状況を報告してもらいました。それを受けて教員からは、「フェーズ1の各学部の知識を『CSR報告書』にどう還元していくのか、報告書の軸をどうしていくのか考え抜いてほしい」というアドバイスがありました。
授業では、まず2チームそれぞれの進捗状況を報告してもらいました。それを受けて教員からは、「フェーズ1の各学部の知識を『CSR報告書』にどう還元していくのか、報告書の軸をどうしていくのか考え抜いてほしい」というアドバイスがありました。
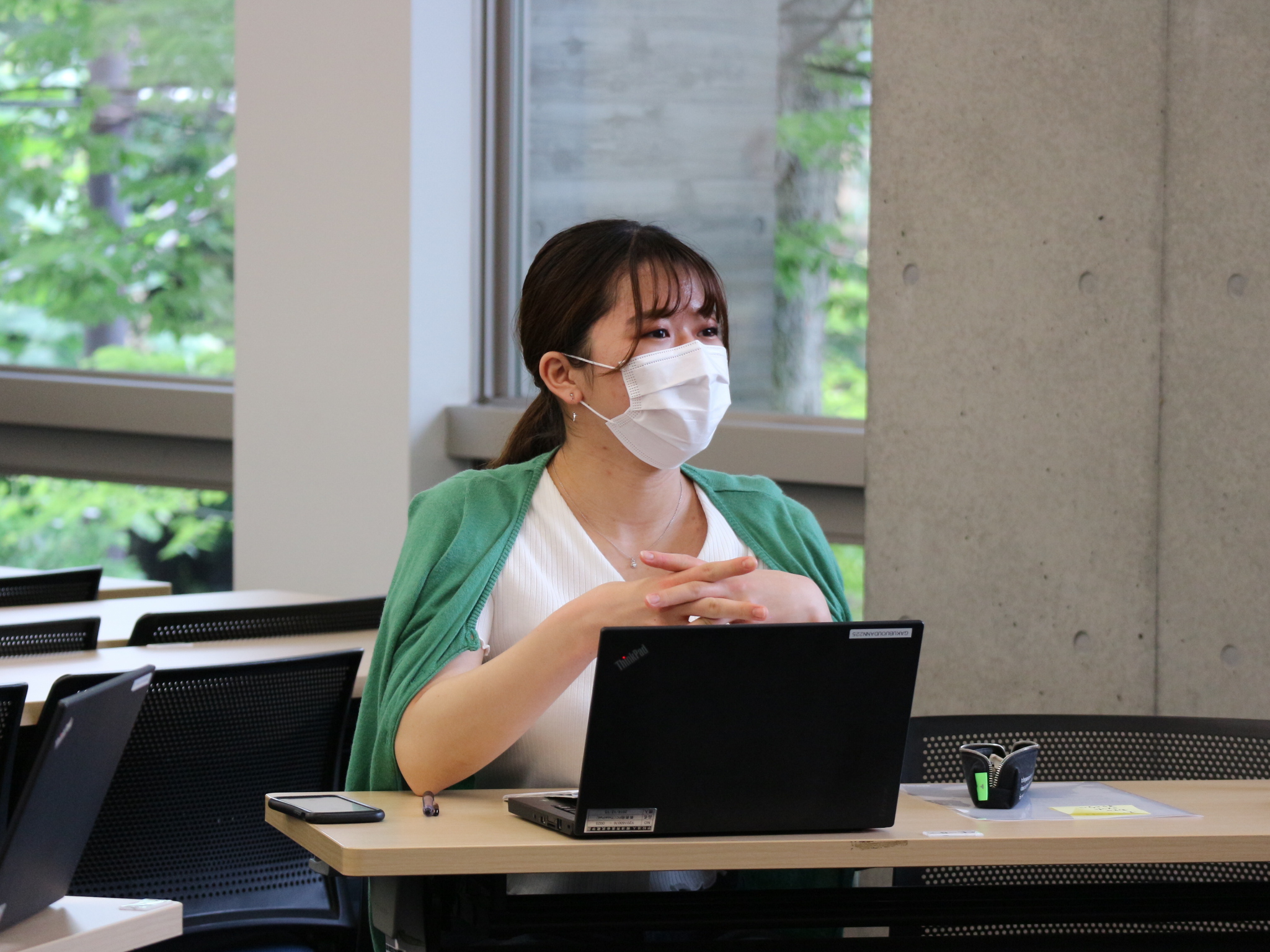
この授業では、課題の『CSR報告書』を作成するために、授業外でも学生たちは話し合いの場を自主的に作っています。先週の授業外の活動では、2チームともにフェーズ1で取り組んだ学部課題の理解を深めるために、教えあうことに時間を費やしたようです。全員が担当する企業について、CSRについて共通した理解をするまでには、時間がかかります。
他学部の学生に教えることで、フェーズ1での情報収集が足りなかったことを実感し、追加で調査する必要があることに気づきます。早速学部チームで調査し直す様子も見られました。
「手間がかかるから」と後回しにしていくと、長い目で見ると自分たちの活動の能率に影響してくるものです。一歩一歩、チームで地道な作業を進めていくしかないようです。
他学部の学生に教えることで、フェーズ1での情報収集が足りなかったことを実感し、追加で調査する必要があることに気づきます。早速学部チームで調査し直す様子も見られました。
「手間がかかるから」と後回しにしていくと、長い目で見ると自分たちの活動の能率に影響してくるものです。一歩一歩、チームで地道な作業を進めていくしかないようです。

授業中は、司会・議事録作成・書記という役割を毎回交代して担当してもらっています。いろいろな立場を経験することで、会議を進めるときにどう工夫していくべきか、会議に主体的に参加するようになると感じています。意見の伝え方、相手の意見に対する聴き方、資料提示の方法、事前予習の必要性など、自分自身の取り組み方を変えていかなければ、チームでの話し合いも良い方向には進んでいきません。
6月28日の授業中には、『CSR報告書』のドラフトを提出してもらうことになっています。チーム活動の状況が、出来栄えに反映されてきます。課題企業やCSRの理解も深めながら、並行してチームのためにどう動けば良いのか、一人一人が主体的に活動してほしいと思います。
6月28日の授業中には、『CSR報告書』のドラフトを提出してもらうことになっています。チーム活動の状況が、出来栄えに反映されてきます。課題企業やCSRの理解も深めながら、並行してチームのためにどう動けば良いのか、一人一人が主体的に活動してほしいと思います。

最後に授業後の学生の日記を紹介します。
「教職の教科方法論で模擬授業を数回やったことがある。今回の司会役はその時に少し似ていた。模擬授業では4~5人の生徒役を相手にしたが、今回はその倍近い人数を相手にしたため、今回の難易度は模擬授業の2倍だった。周りをしっかり見渡して進めていくのは以外に大変だと改めて思い知らされた。それぞれのレベル(理解する速度や自分から積極的意見を言うのが得意か不得意か)を把握して、それにシンクロして進めていくためには、相互理解(チームビルディング)が今後大切だと思った。時間はあまりないが1度は11人で親睦を深める時間も作ってみたい」
「教職の教科方法論で模擬授業を数回やったことがある。今回の司会役はその時に少し似ていた。模擬授業では4~5人の生徒役を相手にしたが、今回はその倍近い人数を相手にしたため、今回の難易度は模擬授業の2倍だった。周りをしっかり見渡して進めていくのは以外に大変だと改めて思い知らされた。それぞれのレベル(理解する速度や自分から積極的意見を言うのが得意か不得意か)を把握して、それにシンクロして進めていくためには、相互理解(チームビルディング)が今後大切だと思った。時間はあまりないが1度は11人で親睦を深める時間も作ってみたい」
