学部横断ゼミブログ

2021.06.03
学部横断チーム・フェーズ2がスタート
ブログ投稿者:学部横断型課題解決プロジェクト運営チーム 伊藤 普子

5月31日(月)の2時限目に、対面とオンラインの同期ハイブリッド型で授業が行われました。学部担当企業チームで活動してきたフェーズ1が5月29日の中間発表会で終了し、今回から三学部が一緒に活動するフェーズ2が始まりました。
授業開始時には、教員から授業用SNSのフェーズ1の総合結果が発表されました。
この授業では、学生同士や企業の担当者とのコミュニケーションをはかる場として、独自に構築したSNSを使用しています。全ての活動をポイント化してみると、メンバーのポイントが平均して高いチームが、自己開示のための良い雰囲気が作れたと読み取れました。
新型コロナウィルス感染拡大の影響で、対面での話し合いができない状況下が続いています。ZoomやSNSなど、仮想空間をうまく使いながら、フェーズ2も取り組んでほしいと思います。
授業開始時には、教員から授業用SNSのフェーズ1の総合結果が発表されました。
この授業では、学生同士や企業の担当者とのコミュニケーションをはかる場として、独自に構築したSNSを使用しています。全ての活動をポイント化してみると、メンバーのポイントが平均して高いチームが、自己開示のための良い雰囲気が作れたと読み取れました。
新型コロナウィルス感染拡大の影響で、対面での話し合いができない状況下が続いています。ZoomやSNSなど、仮想空間をうまく使いながら、フェーズ2も取り組んでほしいと思います。
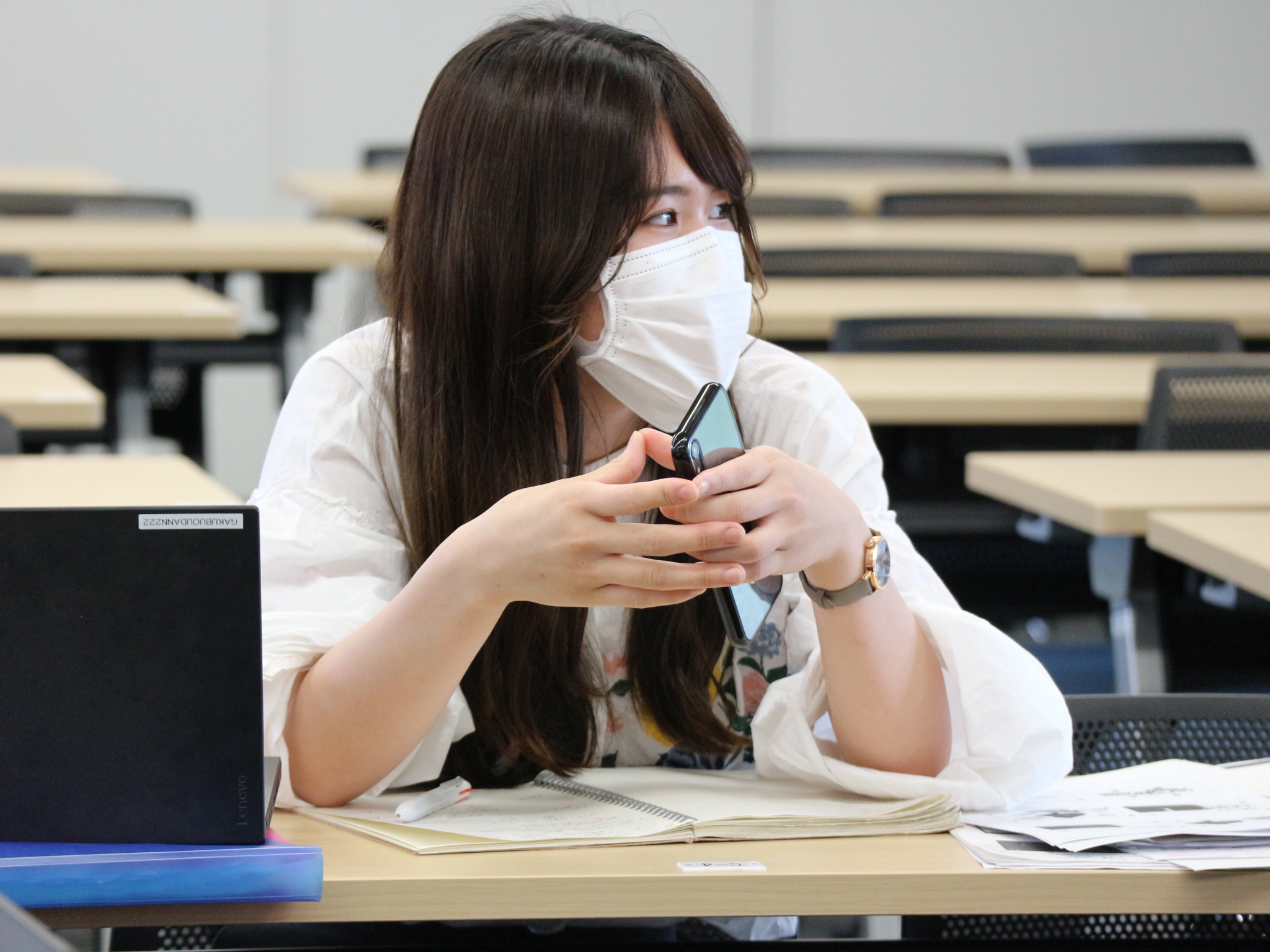
フェーズ2では、チームの人数が一気に三倍になりました。学部チームメンバーにようやく打ち解け、思ったことを発言できるようになった段階から、また一から関係構築をしていかなくてはなりません。今回の授業でも、発言するメンバーが限られ、意見の偏りも見られました。授業後の振り返りの活動日記にも、「人数の多さに怖気づいて発言ができなかった」という感想が見られました。
本プロジェクトの仕組みを、学部チームでの活動の<フェーズ1>と三学部横断チームの<フェーズ2>の2段階に分けたことには理由があります。
課題である『CSR報告書』を作成するというだけではなく、その課題を通して、学生が自分の学部で日々勉強していることが、実社会でどのように役立つのか、どうすれば役立てていけるのか、を立ち止まって考えてもらうためです。
そのため、フェーズ1では各学部の特性を活かさなければできないような調査課題が与えられています。フェーズ2では、フェーズ1での調査結果の情報を共有しつつ、『CSR報告書』の作成にむけてディスカッションを重ねます。そこで、報告書のコンセプトやコンテンツを決定し、記事の執筆やレイアウトを分担します。他学部の専門性に触れる中で、多様な視点を手に入れ、異なる考え方の面白さも知ってほしいという狙いがあります。
本プロジェクトの仕組みを、学部チームでの活動の<フェーズ1>と三学部横断チームの<フェーズ2>の2段階に分けたことには理由があります。
課題である『CSR報告書』を作成するというだけではなく、その課題を通して、学生が自分の学部で日々勉強していることが、実社会でどのように役立つのか、どうすれば役立てていけるのか、を立ち止まって考えてもらうためです。
そのため、フェーズ1では各学部の特性を活かさなければできないような調査課題が与えられています。フェーズ2では、フェーズ1での調査結果の情報を共有しつつ、『CSR報告書』の作成にむけてディスカッションを重ねます。そこで、報告書のコンセプトやコンテンツを決定し、記事の執筆やレイアウトを分担します。他学部の専門性に触れる中で、多様な視点を手に入れ、異なる考え方の面白さも知ってほしいという狙いがあります。

教員からは、「フェーズ2がこの授業の醍醐味」という言葉かけがありました。
他学部の学生との協働作業を通して、たくさんのことを吸収してほしいと思います。
最後に、授業後の学生の日記を紹介します。
「いよいよフェーズ2が始まったが、やはり先の見えない不安が大きい。私たちはまず、フェーズ1で各学部が調査したことを共有することから始めた。同じ企業を調べているが、やはり各学部特有の視点があり面白かった。それと同時に、「共通理解」をどこまでしていく必要があるのか、という疑問を感じた。また、自分たちのフィールドでさえ調査、分析がまだまだ足りないことも痛感した」
他学部の学生との協働作業を通して、たくさんのことを吸収してほしいと思います。
最後に、授業後の学生の日記を紹介します。
「いよいよフェーズ2が始まったが、やはり先の見えない不安が大きい。私たちはまず、フェーズ1で各学部が調査したことを共有することから始めた。同じ企業を調べているが、やはり各学部特有の視点があり面白かった。それと同時に、「共通理解」をどこまでしていく必要があるのか、という疑問を感じた。また、自分たちのフィールドでさえ調査、分析がまだまだ足りないことも痛感した」
