学部横断ゼミブログ

2021.06.02
課題提供企業の担当者の方々に中間発表を実施
ブログ投稿者:学部横断型課題解決プロジェクト運営チーム 伊藤 普子

5月29日(土)の1時限目~5時限目に授業が行われました。今回は、前期授業にご協力いただいているオリエンタルモーター株式会社とスガツネ工業株式会社の担当者の方々をお招きして、各学部の調査結果を発表しました。
授業が開始した4月から学部ごとに分かれて、7月10日の最終報告会で発表する『CSR報告書』の実制作に必要な方針や内容の予備調査を行ってきました。どのチームも5月24日の授業中に行ったプレ発表からさらにブラッシュアップした内容で、努力の跡が垣間見られました。
授業が開始した4月から学部ごとに分かれて、7月10日の最終報告会で発表する『CSR報告書』の実制作に必要な方針や内容の予備調査を行ってきました。どのチームも5月24日の授業中に行ったプレ発表からさらにブラッシュアップした内容で、努力の跡が垣間見られました。

担当企業からは、「よく調べてくれている」「要素がたくさん盛り込みすぎている印象。限られた時間で何を伝えたいかをもう少し明確にしたほうが良い」「今後は調査した内容をより深堀してほしい」「日本企業としてどんな特徴があるかをもっと調べてほしい」など、たくさんのコメントを頂くことができました。学生たちは、コメントを受けて反省する点も多々あったようですが、課題提供企業に対する知識も、学部の専門的視点からの考え方も成長したことを実感し、達成感を感じていました。
お忙しい中、大学まで足を運んで発表を聴いていただいた企業担当者の皆さまには、この場をお借りして御礼申し上げます。
お忙しい中、大学まで足を運んで発表を聴いていただいた企業担当者の皆さまには、この場をお借りして御礼申し上げます。
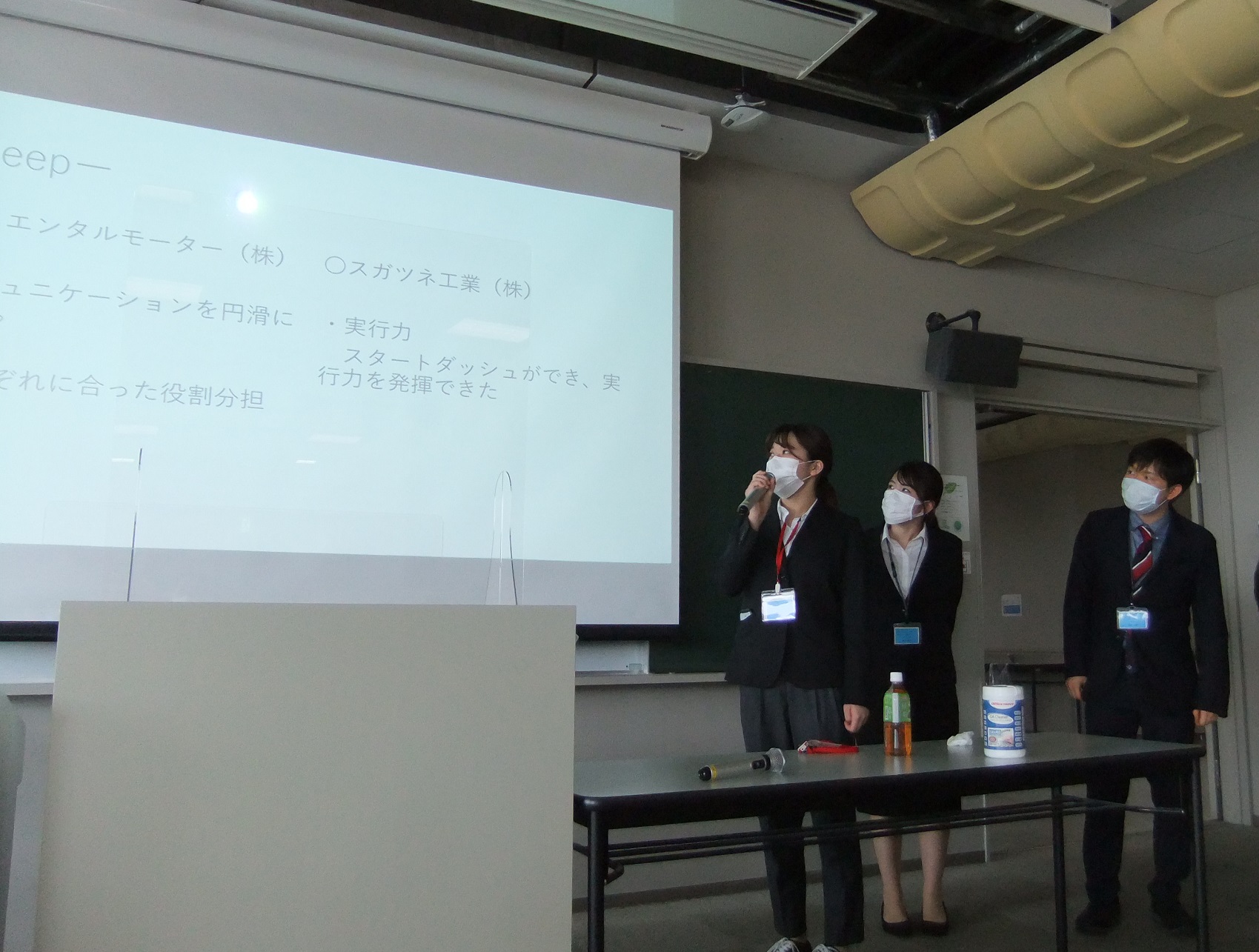
午後は、企業との座談会を終えたあと、これまでの取り組みについて、チームと個人の両方の面で振り返りの時間を設けました。学部担当企業チームでは、「①チームで上手くいった点、②チームの上手くいかなかった点、③②を踏まえて今後はどういうことに気を付けるか」について話し合いをしてもらい、パワーポイントで発表してもらいました。個人の振り返りでは、第2回キャリアコンサルタントとの面談を行い、社会人基礎力の12の項目を指標に伸びた力と伸びなかった力について考えてもらいました。
中間発表会までの学部ごとの活動であるフェーズ1は、2~5名のチームで活動しましたが、学生たちにとっては、チームで活動するということは想像以上に大変であったようです。課題をチームで成し遂げるには、相手の価値観や考え方を受け入れながら、自分との違いがあればそれについて説明をしなければなりません。相手に理解してもらうための説明には、工夫と根気が必要になってきます。互いの考えを分かり合うまでのプロセスには、いろいろなアプローチの方法があることも実感できたようです。
中間発表会までの学部ごとの活動であるフェーズ1は、2~5名のチームで活動しましたが、学生たちにとっては、チームで活動するということは想像以上に大変であったようです。課題をチームで成し遂げるには、相手の価値観や考え方を受け入れながら、自分との違いがあればそれについて説明をしなければなりません。相手に理解してもらうための説明には、工夫と根気が必要になってきます。互いの考えを分かり合うまでのプロセスには、いろいろなアプローチの方法があることも実感できたようです。

中間発表を終えて、これからは学部横断チームでの活動が始まります。10人もしくは11人というチーム構成で、担当する企業の『CSR報告書』を作成していきます。最終報告会までの授業回数は6回です。短い期間ですが、三学部の調査内容から伝えたい内容を決定し、それを表現するための構成をどうするのか、話し合うことは盛りだくさんです。頑張ってほしいと思います。
最後に、中間発表会を終えた学生の日記を紹介します。
「私たちのグループは発表5日前に内容を全て白紙に戻したが、発表に間に合わせることが出来て良かったと思う。正直に言うと、発表に間に合うか不安で諦めそうになった。ただ、SNSを通じて質問に答えてくださったり、休日に大学まで足を運んでくださる企業様に「感謝」の気持ちを伝えたいという思いが原動力に繋がり諦めずに出来た。白紙に戻す決断をした5月24日(発表5日前)はチームで14時から20時まで話し合った。もちろん、その話し合いの中でそれぞれが不安な思いを口にすることがあった。しかしながら、皆諦めることは無くどうしたら間に合うかを真剣に話し合った。このとき私はこのチームで活動してきてよかったと強く感じ、チームメンバーに対しても「感謝」の気持ちが芽生えた」
最後に、中間発表会を終えた学生の日記を紹介します。
「私たちのグループは発表5日前に内容を全て白紙に戻したが、発表に間に合わせることが出来て良かったと思う。正直に言うと、発表に間に合うか不安で諦めそうになった。ただ、SNSを通じて質問に答えてくださったり、休日に大学まで足を運んでくださる企業様に「感謝」の気持ちを伝えたいという思いが原動力に繋がり諦めずに出来た。白紙に戻す決断をした5月24日(発表5日前)はチームで14時から20時まで話し合った。もちろん、その話し合いの中でそれぞれが不安な思いを口にすることがあった。しかしながら、皆諦めることは無くどうしたら間に合うかを真剣に話し合った。このとき私はこのチームで活動してきてよかったと強く感じ、チームメンバーに対しても「感謝」の気持ちが芽生えた」
