学部横断ゼミブログ

2021.04.30
学部に分かれての調査・フェーズ1スタート
ブログ投稿者:学部横断型課題解決プロジェクト運営チーム 伊藤 普子

4月26日(月)の2時限目に授業が行われました。本授業は、本学の<ディプロマポリシー>の中でも、「他者と協働する力」「学びを社会のなかで活用する力」を身に付けることを特に重要な目的としており、教育効果を最大限に創出するために、対面とオンラインの同期ハイブリッド型で授業を実施しています。
今回の授業から5月29日の中間発表会までは、経済学部・人文学部・社会学部と学部ごとに教室を分かれて授業を行う期間(フェーズ1)となります。フェーズ1では、後半(フェーズ2)で作成する担当企業の『CSR報告書』の作成に必要な方針や内容の予備調査を、専門性を生かしながら行っていきます。
本学の建学の理念である、「自ら調べ、自ら考える」の姿勢を大切にし、決められた課題に対してどのように調査・分析を進めていくかは、学生たちの自由です。
学生たちは、今まで学部のゼミや講義で学んできたことを生かし、分からない点は教員に確認しながら調査を進めていきます。やるべきことのイメージがつかない学生も多いようですが、まずは資料探しから動きだし、課題分析のための知識を増やしていきます。
今回の授業から5月29日の中間発表会までは、経済学部・人文学部・社会学部と学部ごとに教室を分かれて授業を行う期間(フェーズ1)となります。フェーズ1では、後半(フェーズ2)で作成する担当企業の『CSR報告書』の作成に必要な方針や内容の予備調査を、専門性を生かしながら行っていきます。
本学の建学の理念である、「自ら調べ、自ら考える」の姿勢を大切にし、決められた課題に対してどのように調査・分析を進めていくかは、学生たちの自由です。
学生たちは、今まで学部のゼミや講義で学んできたことを生かし、分からない点は教員に確認しながら調査を進めていきます。やるべきことのイメージがつかない学生も多いようですが、まずは資料探しから動きだし、課題分析のための知識を増やしていきます。
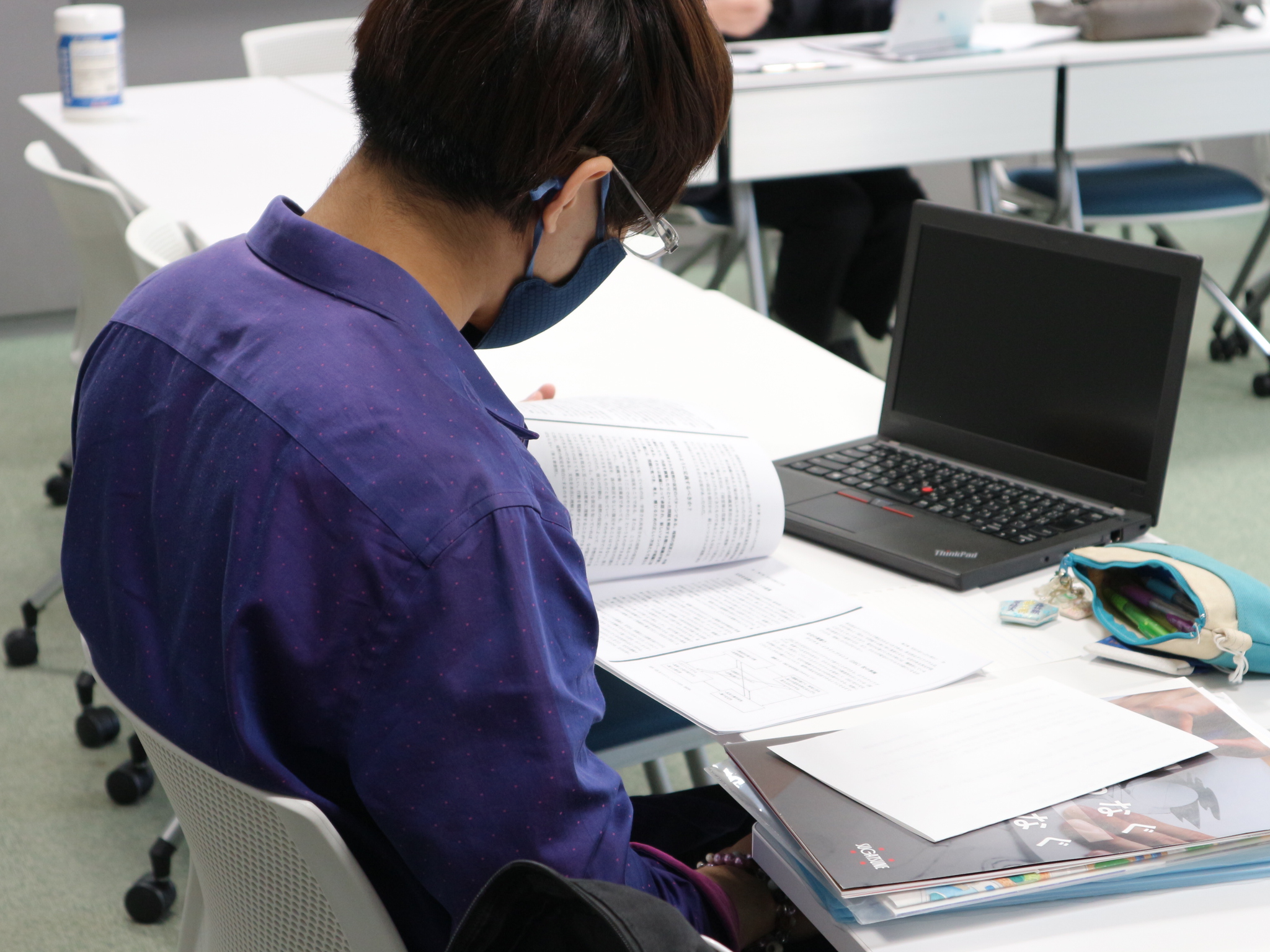
4月24日の合同授業の際に、様々なデータベースの活用方法を教員から教示されました。図書館で関連図書を探したり、インターネットで記事や論文などを検索しながら、お宝になりそうな情報を根気よく探してください。
今年度前期授業は原則オンラインで開始され、対面授業が本授業だけという学生がほとんどです。「大学に登校できることが楽しい」「今まで話したこともなかった人と意見を言い合える環境がうれしい」と、課題は大変ながらも、チームメンバーとの協働作業はとても価値ある時間と感じているようです。授業は3か月という短い期間ですが、チーム活動を楽しみながら課題に取り組んでほしいと思います。
今年度前期授業は原則オンラインで開始され、対面授業が本授業だけという学生がほとんどです。「大学に登校できることが楽しい」「今まで話したこともなかった人と意見を言い合える環境がうれしい」と、課題は大変ながらも、チームメンバーとの協働作業はとても価値ある時間と感じているようです。授業は3か月という短い期間ですが、チーム活動を楽しみながら課題に取り組んでほしいと思います。

最後に学生の授業後の日記を紹介します。
「合同授業が終わり、本格的に課題に挑む日々がスタートした。社会学部として、CSRという概念に向き合っているが、自分の中では多くの情報が入ってくる中で混乱し、「何をしなくてはならないのか」ということが、最初より見えにくくなったのも事実である。
その中で、個人ではなくチーム作業としてやっているメリットも見えてきた。チームリーダーを中心に、「これをいつまでにやろう」と明確に設定していく流れができているので、何をやったらいいかわからないという不安はあまり感じずに済んでいる。
これまでの私は、行き当たりばったりで最終的なゴールしか定めずに物事を行なっていたので、これも計画力の一環として意識していきたい」
「合同授業が終わり、本格的に課題に挑む日々がスタートした。社会学部として、CSRという概念に向き合っているが、自分の中では多くの情報が入ってくる中で混乱し、「何をしなくてはならないのか」ということが、最初より見えにくくなったのも事実である。
その中で、個人ではなくチーム作業としてやっているメリットも見えてきた。チームリーダーを中心に、「これをいつまでにやろう」と明確に設定していく流れができているので、何をやったらいいかわからないという不安はあまり感じずに済んでいる。
これまでの私は、行き当たりばったりで最終的なゴールしか定めずに物事を行なっていたので、これも計画力の一環として意識していきたい」
