学部横断ゼミブログ

2020.11.13
【フェーズ2】三学部横断チームの活動がスタート
ブログ投稿者:学部横断型課題解決プロジェクト運営チーム 伊藤 普子

フェーズ2を開始するにあたって、まずは教員から<フェーズ1の授業用SNSのポイントデータから見えた、チームビルディングと個人の成長>について、パワーポイントで説明しながらフィードバックを行いました。
授業用SNSは日記の自己省察する場と、三学部合同の担当企業グループ・学部別の担当企業グループ・事務連絡・議事録など情報共有していく場に分けて運用しています。使用すればするほど、ポイントが加算していく仕組みになっており、そこからコミュニケーションが円滑に行われているかどうかが見えてきます。
教員からは、「組織運営に必要な情報を自ら取りにくる姿勢、自分から共有しようとする姿勢がSNSのポイントから分かる。常にアンテナをはり、正しい情報を正確にとり、チームを活性化していきましょう」というアドバイスがされていました。
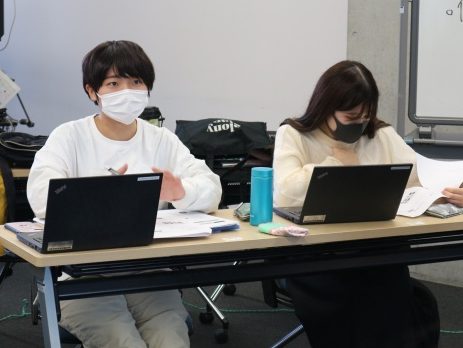
フェーズ2では、フェーズ1で各学部が調査した内容を持ち寄り、三学部合同チームで次の課題に取り組んでいきます。
①どのような視点から担当企業の社会的役割や責任を紹介すべきかテーマ、構成を決める。
②決定した枠組みに従って、三学部合同で『CSR報告書』を作成する。
2チームともに、何から始めればよいのか分からないまま、手探りの状態で話し合いが進みました。久しぶりの対面での話し合いに緊張をしていた学生たちも、授業が進むにつれて活発な意見交換をしている場面が多々見られました。


授業後の学生の日記を紹介します。
「フェーズ1ではやる気故の空回りをしてしまったことから、もともとあまりない自信を喪失していたのだが、働きかけ”られ”た分、”働きかけた”と自信を持っていいんだなと数値を持って思い知らされた。「働きかけ力」が一番ないと思っていたため、先生方やメンバーから言ってもらえた時は大変嬉しかったし、こうして定量的な結果としてでたことは自信に繋がるだろう。だが一方で課題もある。働きかけに対する働きかけ”られ”の差が開いていた点だ。この差は自分の働きかけに対して、助けられている点が大きいことがいえ、このことから自分の働きかけが一方的であったことが考えられる。フェーズ2ではいただいたものを適切に返せるように、他者に”もう一歩”寄り添い、関わり方と行動を”もう一歩”深めていく所存である」
「今まではオンラインで話し合いをしており、何か物足りなさを感じていた。そして今日その足りない何かが明確になった。それは、「空気感」だ。
もちろんフェーズ1でも互いの空気感をある程度は感じることはできていたが、やはり対面だと互いの思っていることが透けて見えるような気がする。
発言だけでなく態度や足を組み替える動作、腕組や頬杖など無意識のうちに表出される行動は、その人が今どんな気持ちで話しているか、あるいは黙っているか、笑っているか、いないかなどを裏付けていると考える。
同じ空気を吸って同じ空間に存在することで、まだ数回しか顔を合わせていない他学部のメンバーのことをスムーズに知ることができるだろう」
