学部横断ゼミブログ

2020.05.27
中間発表会に向けたプレ発表を実施
ブログ投稿者:学部横断型課題解決プロジェクト運営チーム 伊藤 普子

今回は三学部ともに、今週土曜日に行う中間発表会に向けてのプレ発表を実施しました。オンラインでの発表は、タイムラグが発生する関係で、発表者とスライドの画面切り替え担当者との息が合わない場面も見受けられました。
4月中旬から事前課題に取り組み、各学部異なる視点から担当する企業について調査してきました。たくさんの情報をインプットし、伝えたい内容について根拠を明確に示し完成に近づいているチームもあれば、伝える内容があやふやなままプレ発表を迎えたチームもありました。
教員からは「まだまだオリジナリティが足りない」「自分たちの視点を入れてほしい」「言葉の意味を十分に理解できていないと感じる」とたくさんの指摘がされていました。
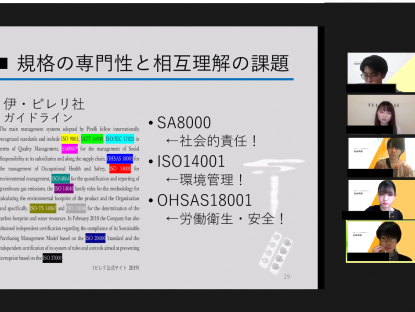
自分たちの課題に対する情報のインプットが多くなればなるほど、「先入観」が出来てしまっているようです。それを受け入れた上で、チームで発表内容を壊すなり、表現の方法を変えるなどをしていかないといけません。
オンラインの授業ではなかなか学生の表情まで読み取ることはできませんが、プレ発表の終了後「へこんだ」「もうこれ以上は考えられない」「見返してやりたい」「三学部横断ゼミの真の大変さ・難しさを痛感した一日だった」という感想が聞かれました。

チームメンバーとのリアルな対面でのミーティングができない中、オンラインでの議論を続けています。教員たちも細かなニュアンスを伝えきれないもどかしさを感じながら、納得できる内容になるまで、指導は続きます。
各学部の課題に答えはありません。そこに対して、チームで真剣に話し合いながら向かっていく面白さや、その過程で自分の気づかなかった能力を感じてもらいたいと思います。
最後に学生の日記を紹介します。
「オリジナリティを出すにはどうしたらいいか。言い換えれば、オリジナリティを出すことを前提にしたインプットとはいかなるものか。それはおそらく、一つの情報を多様な観点から深掘りすることだと思う。そうすれば「一つの情報が気づいたら10の情報につながっていた」みたいな状態になる。誰が、いつ、それを作ったか、そのとき社会はどんな状況だったか、それはどんなものか等々、こうした多様な観点から見る情報は、別の言い方をすれば「先人たち」のオリジナリティといえるのかもしれない。
そしてなによりも、そこから何が言えるか。これをどう言語化するかが、オリジナリティの主な要素であると思う。
オリジナリティの形成は新しい「知」の誕生の瞬間でもあると考えている。仮に私たちの個性の表出が新たな知として、先人たちによる「知」の構築の一端を担うレベルにまでに昇華できれば、それは最高の「プレゼント」になるのではないだろうか」
