学部横断ゼミブログ

2020.05.13
2020年度前期授業スタート
ブログ投稿者:学部横断型課題解決プロジェクト運営チーム 伊藤 普子

今年度前期は、経済学部6名、人文学部7名、社会学部10名の計23名が履修しています。まずは5月30日(土)にオンラインで行う中間発表会に向けて、学部ごとに分かれて課題に取り組んでいます。

今年度の本授業を担当する教員は、下記3名です。
経済学部 大熊美音子 助教
人文学部 代島 克信 客員教授
社会学部 玉置 佑介 助教
開講以来はじめて、LIVE版のオンライン授業となりました。
授業用SNSも活用し、教員と学生はバーチャルでのコミュニケーションを取りながら進めていきます。
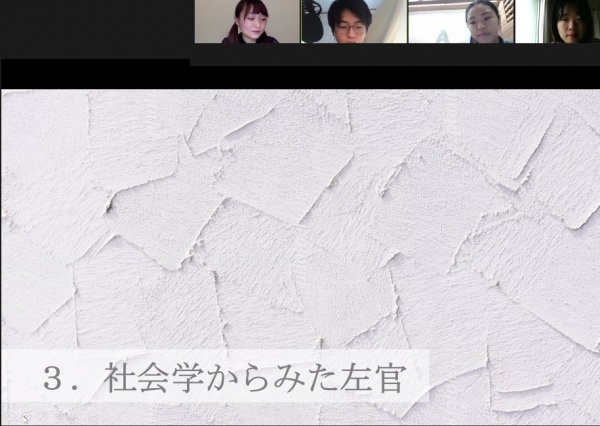
第1回目の授業では、学部ごとにバーチャル教室に分かれて、課題提供企業の業界(左官業、金型)について発表し合いました。経済学・人文学・社会学と各学部の専門性を軸にした発表のため、与えられた課題が同じでも発表内容は違います。教員からは「何を伝えたいのか明確にすること」「発表の軸をどこにおくのか」「自分たちの得た知識から、自分たちが導き出した答えは何かを示すこと」といったコメントがなされていました。
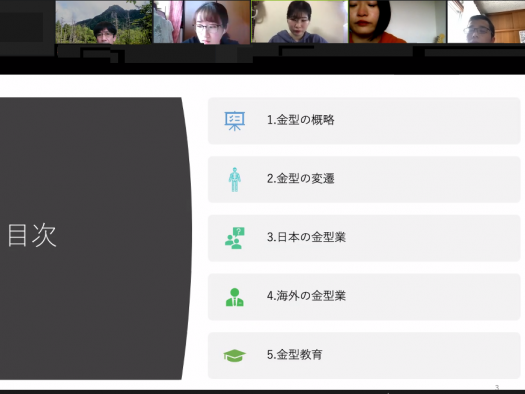
図書館が開館していない状況でも、オンライン上で資料を集めることは可能なはずです。担当企業が用意して下さった資料やホームページも、まだまだ分析を進めれば見えてくることがあるはずです。
「なぜこうなっているのか」「自分たちが考える担当する企業は〇〇である」と一言で表せることができるようになるまで、担当企業について調査を広く深く突き詰めていってください。
「今週は先週に比べて主体的に活動できた。
今までの正解が分からず誰かの行動を見ていただけの自分から「いいものをつくる」という考えを待ち躊躇する事が減った。
しかし、減ったのみで主体性はまだまだ足りない。今までの活動を振り返り、主体性を持つことは創造性や課題発見力も必要になる事が分かった。基本のやるべき事はこなしつつ創造力を働かせて新しい提案をし、最終目標の過程で課題を見つける事が今後求められる。
先生がミーティングでおっしゃっていた「調べた事から何が分かるか、そこからどう結論付けるか」は今の時点での不足部分が顕著に分かるアドバイスであった。常に情報をインプットしつつアウトプットする事を目標にする」
