学部横断ゼミブログ

2019.09.26
三学部横断ゼミの目的
ブログ投稿者:学部横断型課題解決プロジェクト運営チーム 伊藤 普子

9月23日(月)の2時限目に授業が行われました。祝日授業となりましたが、先週の授業に配布した『ガイドブック』の説明や、各担当企業別の学部ごとに分かれての役割分担決め、そしてキャリアコンサルタントとの面談の説明を行いました。
この授業は、異なる学部の学生と一つのチームを作り『CSR報告書の作成』という課題に取り組む中で、次の3つについて育成することを目的としています。
1)社会人基礎力を育成すること
2)正確な自己評価能力を育成すること
3)社会的責任を果たすことの意義と難しさを理解すること
教員からは「何を目的としてやっているかをしっかり考えることで、一つひとつの経験がより深いものになる」という説明がありました。授業の仕組みは複雑で、すぐには理解できないかもしれませんが、『ガイドブック』を何度も読み返し、授業の仕組みを十分に活用して成長してほしいと思います。
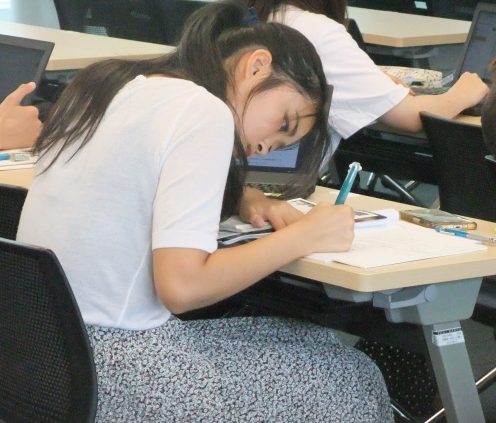
毎回ご協力いただく企業が異なるため、学生たちが作成する『CSR報告書』の内容もさまざまです。担当企業にふさわしい『CSR報告書』に作り上げるには、それぞれのチームで調査・分析する中で答えを探り当てていかなくてはいけません。
授業開始前から学生にはコーポレートガバナンスに関する図書や各学部の課題に関連する文献を読んでもらいました。たくさんの資料を読み、関連する場所に足を運ぶなど、五感を使った作業を大切にしながら、オリジナリティあふれるものを完成させてください。
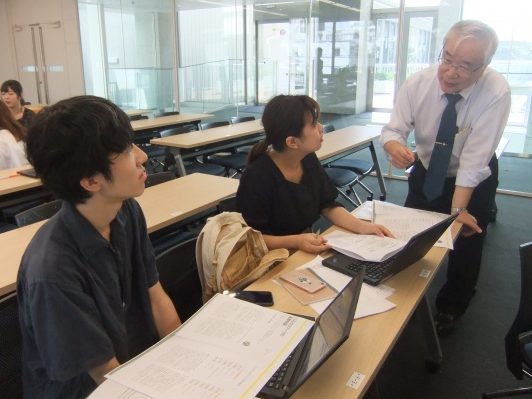
今週の土曜日の授業では、課題提供企業2社からの企業概要のプレゼンテーションを受けるほか、キャリアコンサルタントとの第1回目の面談があります。その面談を受ける前に社会人基礎力の12の力について、自身の状況はどうなのか文章にして提出してもらいます。
チーム活動においては、状況に合った役割を自分自身で見つけることが求められます。自己理解や他者理解がチームワークに影響を及ぼします。<社会人基礎力>という概念をチーム全員が共通言語として用い、その概念に自分やチームメンバーの行動を落とし込むことで、自己理解・他者理解を促進させ、チーム活動が活性化することを期待します。
