学部横断ゼミブログ

2019.06.25
自分の殻を破る
ブログ投稿者:学部横断型課題解決プロジェクト運営チーム 伊藤 普子

6月24日(月)2時限目に授業が行われました。来週の授業ではCSR報告書のドラフト提出が控えていますが、まだまだ「何を伝えたいのか」、全体のコンセプト、構成要素がはっきりとしません。

教員からは授業後に、「企業が行っているCSR活動の具体的内容が見えてこない」「報告書それぞれのページで何を伝えたいのか、意義を考えて作ること」「まだまだオリジナリティが足りない」といった厳しい指摘がありました。学生たちからは、最終発表会まで時間がない中まだ見えてこない全体像に対する不安の表情が読み取れました。
授業後の学生の日記に「もやもやする」「危機感」といった言葉が書かれていました。うまく行っていないことを自覚できているということは、非常に大切なことです。そこには成長のチャンスがあります。
三学部の学生が一緒に活動するフェーズ2では、考え方や物事に対する視点もさまざまで、その中で作業を一緒にしていくからには、どんどんコミュニケーションをとらなくてはなりません。つまずきの大部分は、その「コミュニケーション」に帰着するケースが多いようです。
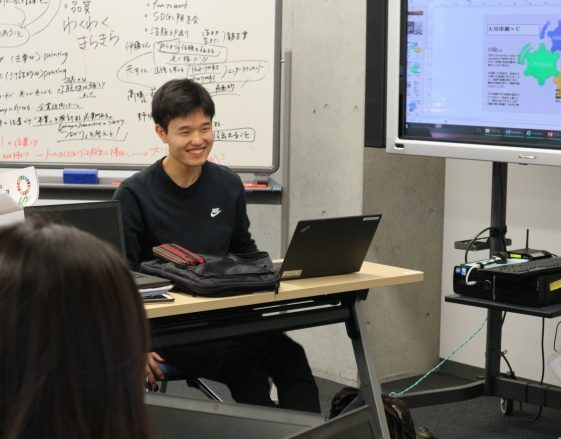
7月13日(土)の最終報告会まで残り3週間となりました。残された時間の過ごし方で、最終報告会の発表内容は大きく変わってきます。焦って何をしているのか分からなくなったのであれば、今の課題をリストにしてみるのも良いでしょう。チームメンバーの意見に納得しないのであれば、しっかりとした根拠を示したうえで発言する勇気も必要でしょう。チームに課されている課題を再確認しながら、自分ができることを考えてみましょう。
この授業の『ガイドブック』の中で、<自分の殻を破る>ことが授業の目的の一つとしてあげられています。今までのやり方のままでうまくいかないのであれば、自分の殻を破って一人ひとりが主体的に行動してほしいと思います。
「私は、「チーム全員」で、この報告書を作り上げたい。というか、チーム全員の力が結集されない限り、既存のものを超える、凌駕する報告書を作りあげることはできないと思う。私もその組織の構成員の一人である。だから、こんな一丁前のようなことを言っているが、できていないのは事実である。
チームにとって「重要な他者」であれるようになりたい。そうなれる場所がここにはあるのだと思う。ここで、今までの自分の経験してきたちっぽけな経験を、実践しなかったら、絶対に後悔する。だから、私は、殻を破りたいし、むしろそうなったときの自分を見てみたい」
