学部横断ゼミブログ

2018.05.10
情報収集
ブログ投稿者:学部横断型課題解決プロジェクト運営チーム 伊藤 普子

5月7日(月)授業が行われました。G.Wを挟んだため2週間ぶりの授業でした。連休中にしっかり活動ができたチームもあれば、個々に調査は進んでいるものの、チームメンバー同士で情報共有ができなかったチームもありました。
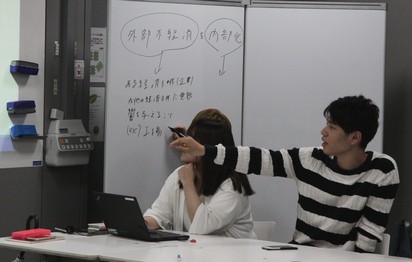
どのチームも分担して作業を進めているようですが、その内容を一人だけで理解していても先に進むことはできません。収集した情報についてチームで意見を出し合い、掘り下げ、チームの発表の核となる部分を見つけられるかがポイントです。
情報収集はどこまで調べれば終わりということはありません。調べれば調べるほど疑問が生じてきます。その疑問に向き合って、そこから見えてきたことを、学生たちはどういった言葉で表現するのでしょうか。まだまだ調査は続きます。
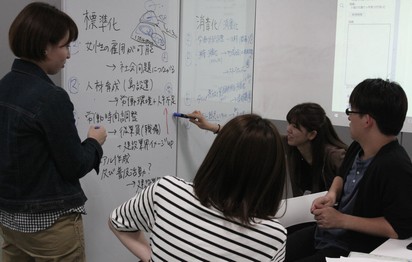
今回のゼミでは、学部内の2チームそれぞれの進捗状況を確認し合う時間も取られました。担当する企業は違うものの、「同じ課題に取り組んでいるのに、このようなアプローチの仕方があったのか」と発見があったようです。また進捗状況が想像したより遅れていると感じ、焦りを感じている学生もいるようです。チーム活動をしているとなかなか思ったように進まないこともあります。「なぜ進まないのか」、「今の自分にはできることは何なのか」と具体的に考える癖をつけてほしいと思います。
最後に授業後の学生の日記を紹介します。
「今まで、自分たちのチームのことで精一杯であったため、他チームのことを気にする余裕がなかった中、今回の情報交換で、それぞれ同じ課題に取り組んでいるのに、他チームの進捗状況、アプローチ方法など、参考にすべき、私たちのものとは異なる情報が入手できて、今回のプロジェクトが個々で取り組むものではなく、チーム、それ以上に全員で取り組むものだということに改めて気がついた」
「GW中にグループで作成したパワーポイントを相手チームと互いに見合い、質疑応答の時間を設けさらに良いものにしていこうと試みた。同時に、先生からもアドバイスを頂いた。相手チームとは進める方向性に差があったがパワーポイントにおいては、どちらが劣っているというものは感じなかった。ただ、私たちよりかはメンバー間のコミュニケーションが取れており、その分円滑な議論がされたことが見て取れた。そのような、目には見えない差を感じ、焦りを覚えた。このままでいいのか、進んでいる方向は正しいのか…。そのような思いがメンバーにもあったのか、来週までの課題が授業内の時間でまとまらなかった」
