学部横断ゼミブログ

2017.05.10
SNSの活用
ブログ投稿者:学部横断型課題解決プロジェクト運営チーム 伊藤 普子

5月8日(月)2時限目に授業が行われました。GW中も各自調査したことを授業用SNSを通してチームで情報共有を活発にしている様子が見受けられたチームもあれば、少しのんびりしてしまったチームもあったようです。
このゼミでは月曜2時限目に行われる授業以外の時間も使って、課題解決のための情報収集・情報共有・密な議論をチームで行っていきます。そのチーム活動を円滑化する1つのツールとしてクローズ型のSNSを導入しています。授業や部活・サークル、アルバイトなど忙しい学生生活の中で、対面で話し合う時間を作れないときにいかにSNSを有効活用するかが、プロジェクトの成功の鍵となります。
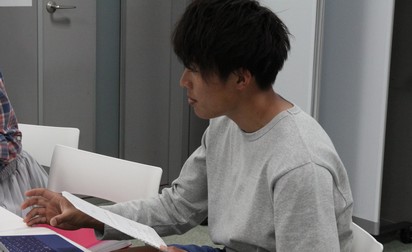
SNSには次のような機能を備えています。
・プロフィール機能
・日記(ブログ)機能
・コミュニティ機能
・メッセージ送受信機能
・ファイルアップ機能
また、日記や各コミュニティにアップしたものをチームメンバーが確認したかどうかわかるように「足あと機能」をつけています。
チーム活動がSNSを通してチームメンバーや教員に視覚化されることで、緊張感を与えゼミ活動を活発化させることも企図しています。

ゼミ活動が進む中、対面ではなかなか発言できなかったり、調査してきたことを簡潔にチームメンバーに伝える難しさを感じたり、さまざまな壁にぶつかっているようです。活動の中で感じる葛藤を授業後の日記でチームメンバーと共有することも、チーム活動の中では大切な情報共有となります。課題を解決するために、仲間と協力して相互作用を起こすためには、お互いの状況を知ることが大切です。それを知る手立てとしてSNSを有効に活用してほしいと思います。
6月3日の中間発表会に向けて折り返し地点を迎えました。まだまだ情報を集めなければいけない中、どのような発表にするのかについても考える時期です。これからは今まで以上の話し合いが必要です。「私たちのチームではこう考えました」と自信にあふれた発表にたどり着けるように、頑張ってほしいと思います。
最後に学生の授業後の日記を紹介します。
「中間発表近づくにつれ、以前と比べ、より計画性や状況は握力が必要になって来たように感じます。進行状況を全員が把握し、それを踏まえた上で、どのように進めるか、自分は何をすべきなのかを一人一人がしっかりと考えていくことが大切だと思いました。『誰かがやってくれる』と自分のことだけを考えて行動するのではなく、『グループのために』を考えて行動していきたいと思います」
「前回の授業では、持ち寄る情報の準備不足により、自分の考えの甘さを痛感させられた。そのため、CSVの概念については前回よりも内容のあるものを共有できたように感じた。しかし、担当企業の業界特性については、自分の中で何を調べて持っていくのかを曖昧にしてしまっていたため、今後の発表では使いづらいものを並べてしまった。そもそも『業界特性』とは何なのかを知らないまま課題に取り掛かってしまったため、もう一度自分の中で納得がいくまで調べることにする」
