学部横断ゼミブログ

2016.10.07
SNSを有効に使う
ブログ投稿者:学部横断型課題解決プロジェクト運営チーム 伊藤 普子

10月3日(月)2時限目と3時限目に授業が行われました。授業は学生が主体的に話し合いを中心に進めていきます。
この授業ではチーム活動の効率を図るために、授業外での情報の共有が重要になってきます。そのために授業専用のSNSを上手に利用するようにと教員から声がかかりました。せっかく各自が文献を読み込んだり、文献を探したりしても、それを事前に報告しお互いの知識のすり合わせを行わなければ、授業中の話し合いを建設的に進めることができないからです。

使用しているSNSでは、次のような機能を設けています。
・プロフィール機能
・掲示板機能
・メッセージ送受信機能
・モバイル版提供機能
さらに掲示板機能は、「日記」「企業と3学部の学生と教員」「3学部の学生と教員」「学部別の学生と教員」「事務連絡」の5つのカテゴリーに分けて使用しています。
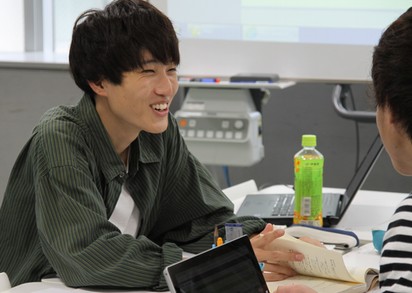

最後に学生の日記を紹介します。
「情報共有の難しさを知った。また、二手に分かれて調べていたため、なおさら情報共有が必要であったと思う。まず、個人の反省点として、自分が調べたことに満足してしまい、それについて深く突き詰めることができなかった。そのため、細かく追求されても答えられないという場面があり、データに載っている数字が正しいかという判断も曖昧であった。これについて言えば、調べることに対しての主体性が欠けていたように思う。チーム全体としての反省点としては、チームで共有したときに、情報に偏りがあったり、同じような情報を持ってきてしまったことで、欲しい情報を手に入れることができなかった」
「調べてくるだけでは意味がなく、相手に自分の調べたことをいかにわかりやすく伝え、理解してもらうかが発表する上で大切だ。私には「発信力」が足りないと今回の授業を通してとても感じた。「発信力」を常に意識し、伸ばしていけるように努力したい」
