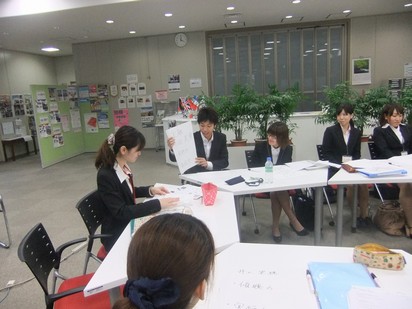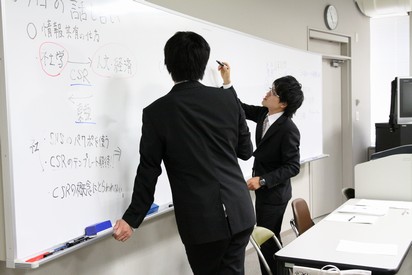6月2日(土)、課題提供企業であるコトブキシーティング株式会社、新日本ビルサービス株式会社、東亜化学工業株式会社の担当者をお招きして、中間発表会を行いました。
フェーズ1がスタートした4月中旬から約1ヵ月半にかけて、経済学部・人文学部・社会学部それぞれに分かれて、各学部の専門知識を生かして課題に取り組んできました。
フェー ズ1では「大学で学んできた学部の特性」を実感することができると思います。ゼミ期間を通して、「議論」することで自分の考えを発信し、他人の意見を吸収 する中で一つの発表にまとめるわけですが、今まで勉強してきた自分の専門性と社会のつながりを感じることができたのではないでしょうか。
満足した形で発表を終えたチーム、不完全燃焼で発表を終えたチーム、それぞれのチームで何が違ったのでしょうか。他のチームの発表を見ることで冷静に自分たちのチームを分析し、フェーズ2でその反省を生かした活動をしたいという日記が多く見られました。
中間発表会を終えた学生の日記を紹介します。
「発表を終えて、自分たちなりの「成功体験」を得たことによって、少なからず、この社会学部のチームのメンバーは「自信」がついたのではないでしょうか。また、自信にも2種類あって、「個人に対する自信」と「チームとしての自信」です。個人に対する自信は、各々が「わたしは、これこれがうまくいった。出来るようになった。」など。大事なのは「チームに対する自信」です。これは、「このメンバーで良かったな。このメンバーなら、この先も何とかなる気がする」と いうものです。発表が終わってから、こういった言葉をチームのメンバーからたくさん聞くことができました。この中間発表で得たこの2つの「自信」を、特に チームに対する自信を、フェーズ2で活かしていきたい。活かさなければ意味がないと感じています。」
中間発表会開催後、午後には企業担当者様への質疑応答、フェーズ1の振り返り(社会人基礎力)のプログラム後、フェーズ2がスタートしました。今回の3チー ムの構成は14人、15人、16人となりました。人数がフェーズ1より約3倍に増えた分、議論の難しさ、専門性の違うメンバーで一つのものまとめることの難しさなど、活動は「難しい」と感じることばかりだと思います。
石森社会学部准教授は、フェーズ2がスタートするにあたり次のように学生たちに呼びかけていました。
「私は、これまで文理融合型の研究プロジェクト(文系と理系の研究者が共同調査等をおこなう研究課題)に度々、参加してきました。自らの経験をとおしていえることは、文理融合とは、文系と理系がたんに「1(文)+1(理)=2」という形になることではありません。私見に過ぎませんが、 「ここからここまでの仕事は文系、ここからここまでの仕事は理系」というパッチワーク的なアウトプット(論文や報告書)の出し方は、あまり興味深くなく、 創造的でもありません。皆さんも考えてみてください。せっかく1つのチームで仕事をしても、「1章~3章 理系からみた椅子」、「4章~6章 文系からみ た椅子」という構成だったら、わざわざ1つのチームを組んで研究した意味が薄れてしまいますよね?それなら最初からバラバラに研究するのと、あまり変わらないでしょう。さまざまな研究分野の人々が集まって時間と場を共有し、一緒に打ち合わせし、一緒に研究をおこない、一緒に汗水を垂らしてフィールドワーク をおこなう。こうした作業を共同でおこなうのであれば、「1(文)+1(理)=無限大」といったら言い過ぎですが、少なくとも既存の文理の枠組みを超えるような「新しいもの」が創造されるべきと思うのです。それは明らかに「1+1=2」以上の何かであり、新しい可能性を秘めているものだと思います。(中 略)。皆さんの場合は「学部横断」ですね。「学部」に関しては、経済・人文・社会ですから、文理融合ではなく、「文文融合」といえますが、1つの方向を目 指して共同作業することに変わりありません。
「横断」とは、「異なる分野・種類などを超えてつながること」を意味します。皆さんの最終的なアウトプット (最終報告およびCSR報告書)という「料理」ができあがったとき、1つの皿のうえで三学部の味が完全にバラバラに盛られているというよりは(そのような箇所もあって然るべきですが)、全体としては、三学部でハーモニーを奏でるような味、たんなる「1+1+1=3」以上の、これまで味わったことのないような魅惑の味になることを期待しています。」
7月7日の学内報告会に向けたフェーズ2の活動がどのような形で各チームが活動を進めていくのか、見守りたいと思います。