リベラルアーツ&サイエンス教育ブログ

2012.08.30
- 国東農業研修
国東農業研修レポート完成
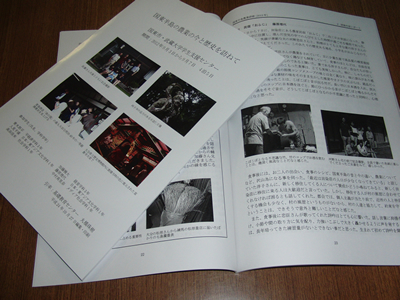
2012年度「国東半島の農業の今と歴史を訪ねて」研修レポートが完成しました。以下は、参加学生のレポートからの抜粋です。彼らの学びの一端を理解して いただければ幸いです。今、日本の大学では課題発見型の教育、強い学びの動機、他者への眼差しなど、激動の時代を落ち着いて切り開く若者を育てるには何が でくるか、模索が続いています。少人数のフィールドワークと農業を組み合わたこの研修旅行は、その試みの一つです。
各学生のレポート内容と写真とは特に関連はありませんが、研修の雰囲気を伝える写真を選んで挿入しました。
各学生のレポート内容と写真とは特に関連はありませんが、研修の雰囲気を伝える写真を選んで挿入しました。
**************************************************
これらは、大分県立歴史博物館での櫻井さんのお話にあった、「当時当たり前のように作ったり使ったりしていたものにはいちいちデータを記録しない」とい うことと繋がっているように思う。現代の私たちの生活でもそうだが、よく考えると今自分たちの身の回りにあるものは、何世紀もすれば古代の遺産となるわけ であり、あまりに雑に扱っていたと反省させられる。
歴史を辿って保存するということに関しては、今回営業日の都合で最後に寄ったからあげ花ちゃんの奥さんが語ってくれた、武蔵大学人文学部日本史演習編の 『大分県国東半島 武蔵町の民俗』が実際に役に立った話がある。この本には、今や誰も正確には覚えていない武蔵町特有のお手玉の数え歌を、何とか調べ挙げ て載せている。これを読んで、奥さんが披露したところお年寄りの方に大盛況だったそうだ。櫻井さんが、レプリカには実物が失われたら新しく文化財になる、 歴史保存の役割があるとおっしゃっていたように、伝統や文化は形として残していくべきなのだと強く感じた。
これらは、大分県立歴史博物館での櫻井さんのお話にあった、「当時当たり前のように作ったり使ったりしていたものにはいちいちデータを記録しない」とい うことと繋がっているように思う。現代の私たちの生活でもそうだが、よく考えると今自分たちの身の回りにあるものは、何世紀もすれば古代の遺産となるわけ であり、あまりに雑に扱っていたと反省させられる。
歴史を辿って保存するということに関しては、今回営業日の都合で最後に寄ったからあげ花ちゃんの奥さんが語ってくれた、武蔵大学人文学部日本史演習編の 『大分県国東半島 武蔵町の民俗』が実際に役に立った話がある。この本には、今や誰も正確には覚えていない武蔵町特有のお手玉の数え歌を、何とか調べ挙げ て載せている。これを読んで、奥さんが披露したところお年寄りの方に大盛況だったそうだ。櫻井さんが、レプリカには実物が失われたら新しく文化財になる、 歴史保存の役割があるとおっしゃっていたように、伝統や文化は形として残していくべきなのだと強く感じた。
-

大分空港の敷地に隣接して設置されている、武蔵町の農産品販売所「里の駅武蔵」で店長さんから野菜の説明を受けている -

「里の駅武蔵」には食堂が付随していて、武蔵町の野菜を調理した美味しい定食を提供している。私たちは六種類のメニューをすべて注文してお互いに交換しながら食べてみたが、どれも地の美味しい野菜を楽しむことができた
**************************************************
交流会では、みなさんが歓迎してくれて、地元の人と色んな話ができて良かった。特に、市長さんとお話しできたことは地域の住民との関わり方に関して良い 勉強になった。市をまとめている方と町の人との距離が近いことには驚きだった。人との関わりが薄れていく現代社会において、地域の人々との距離は離れていく一方、武蔵町のようなあったかい交流関係を見習わなければならないのかもしれない。
そして農業体験では、農家の人々は私たちの食を支えてくれているのだと実感した。ねぎ作業はほんのわずかしか体験できなかったが、お客さんがどのような 野菜を求めているか、ニーズにあっているかなど考えることがたくさんあった。実際、長廣さんの畑を見学に行かせて頂いて農家の大変な面を知ることもでき た。ビニールハウスが閉じていると80度くらいにも温度が上がり、中での作業は過酷なものである。また定量出荷の難しさなど様々ある。
交流会では、みなさんが歓迎してくれて、地元の人と色んな話ができて良かった。特に、市長さんとお話しできたことは地域の住民との関わり方に関して良い 勉強になった。市をまとめている方と町の人との距離が近いことには驚きだった。人との関わりが薄れていく現代社会において、地域の人々との距離は離れていく一方、武蔵町のようなあったかい交流関係を見習わなければならないのかもしれない。
そして農業体験では、農家の人々は私たちの食を支えてくれているのだと実感した。ねぎ作業はほんのわずかしか体験できなかったが、お客さんがどのような 野菜を求めているか、ニーズにあっているかなど考えることがたくさんあった。実際、長廣さんの畑を見学に行かせて頂いて農家の大変な面を知ることもでき た。ビニールハウスが閉じていると80度くらいにも温度が上がり、中での作業は過酷なものである。また定量出荷の難しさなど様々ある。
-

都留ぶどう農園で出荷前の調整作業をしているところ。小ぶりな粒や痛みかけている粒を取り除き、パックに詰める前作業を行っている -

かつてはどの農家にもあったうどん製造器。戦後の農繁期、こどもたちは遊びに行く前には、必ず親から指示された量のうどんを作ってからでないと遊びには行けなかったそうだ
**************************************************
消費者が食材に興味を持ち、その理解が深まることで従来消費者からあまり注目されなかった食材にも利用価値が生まれ、最終的に農作物の廃棄やつくり過ぎ といった事態を回避できるのではないだろうか。自然と人間のバランスを大きく左右する「食」であるが、バランスを上手く保つためには消費者の「食」に対す る見方の向上、そのためにまず消費者の食材に対する理解を深めることが重要だと感じた。
河野了先生は言う「歴史とは歩くことだ」と。現場で起きていることは机上で考えているだけではいつまでたっても知ることはできず、実際に見聞きしなけれ ばわからない。今回、国東半島農業研修に参加することで、農業の厳しさや大変さ、自然との共生の術を知ることもできたが、どこか自分には程遠い関係のない ことと捉えていた高齢化や地域の過疎化という社会問題の実情を知ることができた。そういった意味合いで、この研修に参加して自分の求めていた以上のものが 得られたように思う。
消費者が食材に興味を持ち、その理解が深まることで従来消費者からあまり注目されなかった食材にも利用価値が生まれ、最終的に農作物の廃棄やつくり過ぎ といった事態を回避できるのではないだろうか。自然と人間のバランスを大きく左右する「食」であるが、バランスを上手く保つためには消費者の「食」に対す る見方の向上、そのためにまず消費者の食材に対する理解を深めることが重要だと感じた。
河野了先生は言う「歴史とは歩くことだ」と。現場で起きていることは机上で考えているだけではいつまでたっても知ることはできず、実際に見聞きしなけれ ばわからない。今回、国東半島農業研修に参加することで、農業の厳しさや大変さ、自然との共生の術を知ることもできたが、どこか自分には程遠い関係のない ことと捉えていた高齢化や地域の過疎化という社会問題の実情を知ることができた。そういった意味合いで、この研修に参加して自分の求めていた以上のものが 得られたように思う。
-

国東半島の真ん中にそびえる両子山の懐に建つ由緒ある両子寺にて。急に降り出した激しい雷雨の中、大粒の雨を見つめて歴史を振り返る女学生 -

国東半島の山は、水で浸食され易い凝灰岩という岩でできているので、いたる所に奇岩や岩壁がある。神々しい自然の造形の場所には浅く彫られた仏が刻まれていることが多い。仏像の傍には国東塔といわれる特徴的な石造があった
**************************************************
今回の研修を通じて実際現地に行かなければ分からないことは沢山あることに気が付いた。例えば富貴寺は、教科書の写真でしか見たことがなかったが、現地 に行くことで、現物を観察したり、直接触れたり、独特の空気感を感じることによって、教科書を見ただけでは分からなかった富貴寺の独特の雰囲気を感じるこ とができた。「百聞は一見に如かず」とは、まさにこのことを表すのだと理解した。
国東半島では、沢山の人と出会い、初めての事にも挑戦し、色々な視点から物事を考え、学ぶことによって、視野が広がり大きく成長できたと思う。とても刺 激的な毎日だった。たった五日間という短い間だったが、充実した濃い時間を過ごせたとともに、国東半島に対して、以前から暮らしていたのではないかと錯覚 する程強い親しみを覚えた。まるで第二の故郷ができたような気分で、とても幸せだ。
一度しかない人生、より多くの物を自分の目で見て、より多くの事を体験し感じて、 そして、自分が感じたことをより多くの人に伝えていける人になりたいと思う。今回この研修でお世話になった多くの方々への出会いに感謝したい。本当に有難うございました。
今回の研修を通じて実際現地に行かなければ分からないことは沢山あることに気が付いた。例えば富貴寺は、教科書の写真でしか見たことがなかったが、現地 に行くことで、現物を観察したり、直接触れたり、独特の空気感を感じることによって、教科書を見ただけでは分からなかった富貴寺の独特の雰囲気を感じるこ とができた。「百聞は一見に如かず」とは、まさにこのことを表すのだと理解した。
国東半島では、沢山の人と出会い、初めての事にも挑戦し、色々な視点から物事を考え、学ぶことによって、視野が広がり大きく成長できたと思う。とても刺 激的な毎日だった。たった五日間という短い間だったが、充実した濃い時間を過ごせたとともに、国東半島に対して、以前から暮らしていたのではないかと錯覚 する程強い親しみを覚えた。まるで第二の故郷ができたような気分で、とても幸せだ。
一度しかない人生、より多くの物を自分の目で見て、より多くの事を体験し感じて、 そして、自分が感じたことをより多くの人に伝えていける人になりたいと思う。今回この研修でお世話になった多くの方々への出会いに感謝したい。本当に有難うございました。
-

三浦梅園記念館では江戸時代の哲学者三浦梅園の業績と生涯が、オリジナルな資料とともに展示されている。学芸員の浜田さんから分かりやすい解説をしていただいた -

豊後高田市田染の盆地に入る所に位置している三の宮の断崖、九州では耶馬といわれる凝灰岩の大岸壁である
**************************************************
研修前の事前レポートでは、「知らない場所が自分のかかわり、つながりのある場所へと変わる感動を国東半島で味わいたい。」と述べたが、実際に行って実 現出来たように感じる。最初国東半島のことを“こくとうはんとう”と呼ぶ位全然知らなかった場所が今では、研修中知り合った方々の顔や国東半島の田んぼや 自然をすぐ連想することができる。今なお国東半島の方々とメールや手紙のやりとりで交流が続いている。その様な自分にとって思い入れの強い場所となった国 東半島。そんな思い出が沢山できた研修の旅だった。
研修前の事前レポートでは、「知らない場所が自分のかかわり、つながりのある場所へと変わる感動を国東半島で味わいたい。」と述べたが、実際に行って実 現出来たように感じる。最初国東半島のことを“こくとうはんとう”と呼ぶ位全然知らなかった場所が今では、研修中知り合った方々の顔や国東半島の田んぼや 自然をすぐ連想することができる。今なお国東半島の方々とメールや手紙のやりとりで交流が続いている。その様な自分にとって思い入れの強い場所となった国 東半島。そんな思い出が沢山できた研修の旅だった。
-

けんのき井堰は、この地域の田を灌漑する最も大切な井堰である。左の岩壁に沿って溝が掘り込まれ、配水されている。田染小崎の棚田は、歴史的重要景観として文化財に指定されている -

雨引社の小さな鳥居がみえる。ここには湧水があり、この地域の水田開発の始まりであったと伝えられていて、始祖の場を神社として祀ったのだろう
**************************************************
そしてなにより大きなインパクトを与えられたのは自然の雄大さです。国東での農業体験は時間こそ短かったものの内容は非常に濃いものとなりました。私は 小ねぎ農家にお世話になりましたが、種まきから収穫までの過程はどれもこれも手間暇がかかり、よい作物をしかも計画的に届けようと毎日作業している生産者 の気持ちを少しでも垣間見ることができました。今までは、生産者の農業に対する気持ちや苦労、またそれらを知らないでなんとなく商品を購入していた私は、 あまりに無知だったことが申し訳なく思えてきました。しかしこれからは、新たな視点から見ることができたのでもっと関心を向けていこうと決めました。
私は今回の研修旅行に参加するにあたり、何事にも直接触れて体験してくると決めていましたが、毎日がとても充実していたので満足感を感じながら帰路に着 くことができました。このようなかたちで研修を終えられたのも多くの方々のご支援のおかげだと思っています。今回出会ったすべての方々のお人柄の良さと優 しさは忘れることはできません。研修旅行を終えた今、これから生きていくうえでの大切な知恵や人の温かさを再認識することができ、本当に素敵な四泊五日 だったと思います。
そしてなにより大きなインパクトを与えられたのは自然の雄大さです。国東での農業体験は時間こそ短かったものの内容は非常に濃いものとなりました。私は 小ねぎ農家にお世話になりましたが、種まきから収穫までの過程はどれもこれも手間暇がかかり、よい作物をしかも計画的に届けようと毎日作業している生産者 の気持ちを少しでも垣間見ることができました。今までは、生産者の農業に対する気持ちや苦労、またそれらを知らないでなんとなく商品を購入していた私は、 あまりに無知だったことが申し訳なく思えてきました。しかしこれからは、新たな視点から見ることができたのでもっと関心を向けていこうと決めました。
私は今回の研修旅行に参加するにあたり、何事にも直接触れて体験してくると決めていましたが、毎日がとても充実していたので満足感を感じながら帰路に着 くことができました。このようなかたちで研修を終えられたのも多くの方々のご支援のおかげだと思っています。今回出会ったすべての方々のお人柄の良さと優 しさは忘れることはできません。研修旅行を終えた今、これから生きていくうえでの大切な知恵や人の温かさを再認識することができ、本当に素敵な四泊五日 だったと思います。
-

元宮の磨崖仏は、国東半島らしい特徴がはっきりと現れている浅い彫りの仏である。写真の右には柱のほぞ穴(四角な穴)があることから屋根が懸けられ、床があるお堂が建てられていたことがわかる -

田染の田では、大きなアオサギを何度も見かけた。シラサギもいたが、アオサギの大きさには驚いた -

平田井堰は、平安時代に建造され、600町歩もの水田を灌漑した大規模開発の歴史遺産である。今でいう公共土木だが、この800年間一度も壊れたことがないらしい。場所の選定、優れた土木技術など一度訪れると忘れることのない強い印象を受ける風景である -

宇佐八幡宮の本殿へ向かう大鳥居は、神域に似つかわしいものだった。田染はこの神社の最も重要な荘園であり、国宝富貴寺など多くの貴重な文化財が残されている
