人文学部ゼミブログ
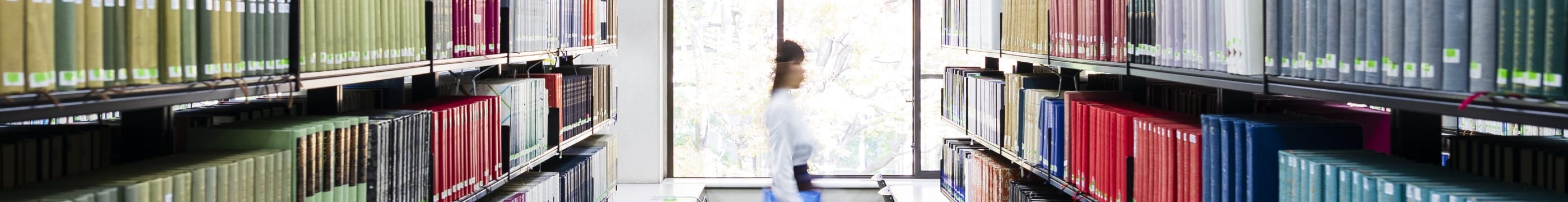
2024.08.08
- 人文学部
- 英語英米文化学科
アート作品におけるジェスチャーやポーズの描かれ方
ブログ投稿者:英語英米文化学科 准教授 岩佐愛

アート作品を鑑賞する際には、描かれた人物の身振りやその意味について知ることが、ときに重要となります。しかし、ふだんから見慣れたしぐさには見逃しがちなものも多くあります。逆に見慣れた作品であっても人物の身振りがさまざまな「感情」を表すことに気づくことで、今まで気づかなかった意味を知ることもあるでしょう。誰もが見過ごしがちな、こうした身振りやしぐさに注目する試みのひとつとして、ゼミでは動物行動学者デズモンド・モリスの『アートにみる身ぶりとしぐさの文化史』(Postures: Body Language in Art, 2019)で扱われる項目を中心に、さまざまなアート作品に表現された人間の身ぶりやしぐさについて学んでゆきます。
春学期は約9週間かけて、12種類の身ぶりやしぐさについての項目の講読を行い、引用されているアート作品の分析を行ってもらいました。この本では英米の作品にとどまらず有史以前のアートや初期の宗教画、現代アート、民芸品、ストリートアートまで幅広い芸術作品が分析対象となっています。そのため、普段の「英米の芸術」講義では取り上げる機会の少ない種類のさまざまなアート作品に触れてもらうこと、加えて「2年次ゼミナール」で毎年取り上げているアートの形態分析のスキルを活かす場としても意図されています。また、英語英米文化学科では自身の所属するコース以外の専門ゼミを選ぶことができるため、文学・芸術・メディアコースに属さない学生の関心にも応える内容として、異文化コミュニケーションにおける非言語コミュニケーションの話題を取り上げています。
レジュメや図版スライドの作成方法など、ゼミでの学習に必要なスキルを身につけつつ、ひとつひとつのアート作品について詳しく調べ、考えをめぐらせることで、今後の人生にも役立つ何かを見つけてもらえればと思っています。
春学期は約9週間かけて、12種類の身ぶりやしぐさについての項目の講読を行い、引用されているアート作品の分析を行ってもらいました。この本では英米の作品にとどまらず有史以前のアートや初期の宗教画、現代アート、民芸品、ストリートアートまで幅広い芸術作品が分析対象となっています。そのため、普段の「英米の芸術」講義では取り上げる機会の少ない種類のさまざまなアート作品に触れてもらうこと、加えて「2年次ゼミナール」で毎年取り上げているアートの形態分析のスキルを活かす場としても意図されています。また、英語英米文化学科では自身の所属するコース以外の専門ゼミを選ぶことができるため、文学・芸術・メディアコースに属さない学生の関心にも応える内容として、異文化コミュニケーションにおける非言語コミュニケーションの話題を取り上げています。
レジュメや図版スライドの作成方法など、ゼミでの学習に必要なスキルを身につけつつ、ひとつひとつのアート作品について詳しく調べ、考えをめぐらせることで、今後の人生にも役立つ何かを見つけてもらえればと思っています。
