人文学部ゼミブログ

2024.06.19
- 人文学部
- 日本・東アジア文化学科
ある音楽家の台湾、中国、そして日本
ブログ投稿者:日本・東アジア文化学科 教授 水口拓寿
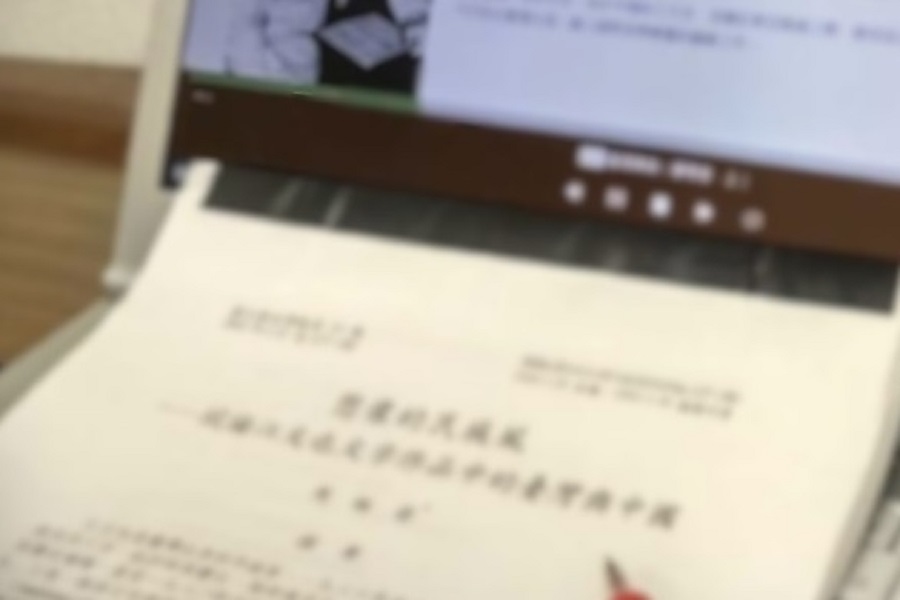
私は中国思想史演習という科目を担当していますが、科目名に含まれる「中国」を「広く中国語圏に関係する」と解釈した上で、毎年違うテーマや教材を選んできました。
昨年度の演習では、植民地時代の台北に生を享け、大戦前夜の東京やベルリンで名を揚げた後、共産政権下の北京で窮死した音楽家・江文也(こうぶんや、1910~1983)に焦点を当てました。時代の荒波に弄ばれ続けた彼の心の軌跡を、思想史という角度から追いかけてゆくために、台湾の学者・周婉窈氏の論文「想像的民族風:試論江文也文字作品中的臺灣與中國(想像された民族風:江文也の文字作品における台湾と中国について試論する)」(『臺大歴史學報』35期、2005)を全員で精読した他、この論文でも言及された江文也の日本語著作『上代支那正楽考:孔子の音楽論』(三省堂、1942)に目を向けたり、彼がベルリン五輪の芸術部門に「日本代表」として出品し、国際的な名声に繋がった「台湾舞曲」(1936)など、様々なジャンルの音楽作品に耳を傾けたりもしました。
周氏の論文の要旨は、次の通りです。江文也は故郷である台湾に強い愛着を抱いていた一方、中国の大陸的な風物や文化伝統に憧れを燃やしていました。そして、これらの気持ちを音楽や文字に繰り返し表現したのですが、しかし彼は、必ずしも現実の台湾や中国を見つめていたわけでなく、むしろ自分の奔放で浪漫的な想像力を、台湾や中国というスクリーンに投影することに相当熱心であったと言えます。なおかつ、彼が発揮した想像力の具体的な中身は、昭和前期の日本における知識人たちの関心や好みと、決して無関係に形成されたものではなかったのです。
論文が世に問われた頃、江文也を台湾の学者は台湾人として、中国の学者は中国人として、日本の学者は日本人として語りたがる(ひいては美化したがる)傾向があり、三者三様のイデオロギーのせいで、彼の本当の姿が見え難くなっていたことは否めません。陰鬱な状況に風穴を開けた長篇の論文を、台湾で使われる繁体字表記の中国語を通して厳密に読み、討論のための材料にするというのは、学生諸君にとって容易な営みでなかったはずですが、皆さんそれぞれに奮闘を重ねて、日本を含む20世紀東アジアの思想史の一隅を、よく照らし出してくれたと思います。副産物として、中国語のリーディング能力もずいぶん上がりました。
昨年度の演習では、植民地時代の台北に生を享け、大戦前夜の東京やベルリンで名を揚げた後、共産政権下の北京で窮死した音楽家・江文也(こうぶんや、1910~1983)に焦点を当てました。時代の荒波に弄ばれ続けた彼の心の軌跡を、思想史という角度から追いかけてゆくために、台湾の学者・周婉窈氏の論文「想像的民族風:試論江文也文字作品中的臺灣與中國(想像された民族風:江文也の文字作品における台湾と中国について試論する)」(『臺大歴史學報』35期、2005)を全員で精読した他、この論文でも言及された江文也の日本語著作『上代支那正楽考:孔子の音楽論』(三省堂、1942)に目を向けたり、彼がベルリン五輪の芸術部門に「日本代表」として出品し、国際的な名声に繋がった「台湾舞曲」(1936)など、様々なジャンルの音楽作品に耳を傾けたりもしました。
周氏の論文の要旨は、次の通りです。江文也は故郷である台湾に強い愛着を抱いていた一方、中国の大陸的な風物や文化伝統に憧れを燃やしていました。そして、これらの気持ちを音楽や文字に繰り返し表現したのですが、しかし彼は、必ずしも現実の台湾や中国を見つめていたわけでなく、むしろ自分の奔放で浪漫的な想像力を、台湾や中国というスクリーンに投影することに相当熱心であったと言えます。なおかつ、彼が発揮した想像力の具体的な中身は、昭和前期の日本における知識人たちの関心や好みと、決して無関係に形成されたものではなかったのです。
論文が世に問われた頃、江文也を台湾の学者は台湾人として、中国の学者は中国人として、日本の学者は日本人として語りたがる(ひいては美化したがる)傾向があり、三者三様のイデオロギーのせいで、彼の本当の姿が見え難くなっていたことは否めません。陰鬱な状況に風穴を開けた長篇の論文を、台湾で使われる繁体字表記の中国語を通して厳密に読み、討論のための材料にするというのは、学生諸君にとって容易な営みでなかったはずですが、皆さんそれぞれに奮闘を重ねて、日本を含む20世紀東アジアの思想史の一隅を、よく照らし出してくれたと思います。副産物として、中国語のリーディング能力もずいぶん上がりました。
