人文学部ゼミブログ
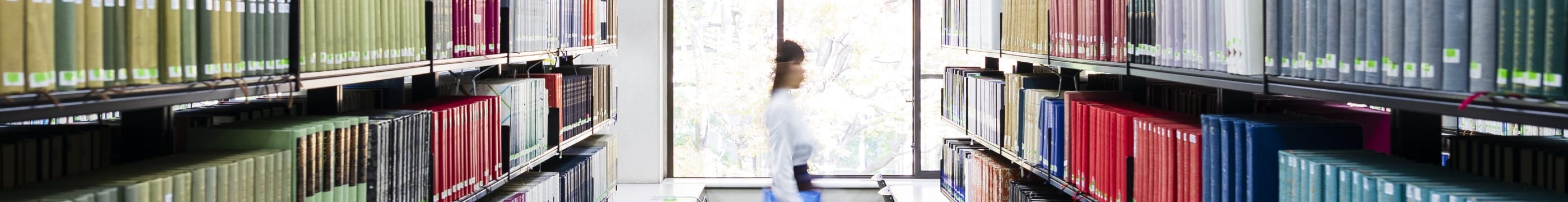
2016.07.26
- 人文学部
- 日本・東アジア文化学科
江戸のことばと文化を肌で感ずる下町散歩
ブログ投稿者:日本・東アジア文化学科 教授 小川 栄一

「日本の言語文化演習」では江戸のことばや文化の研究を行っています。6月11日(土)午後、有志10名が集まって、東京生まれの女流作家、樋口一葉の記念館を始め、江戸情緒が残る下町を見学してきました。関東大震災や戦災などで下町の伝統的な町並みの多くは失われましたが、人々の風俗、気質、ことばは江戸・近代文学に残されています。
まず一葉記念館では、ボランティアの方の説明を聞いて一葉の原稿や手紙を閲覧しました。彼女の代表作『たけくらべ』の一節を紹介しましょう。
さすがに流麗な文体ですね。大門、見返り柳、お歯黒どぶといえば吉原遊郭のこと。吉原近くの華やかな大音寺前の町を舞台に、少年少女の淡い恋心が描かれています。一葉も吉原の近くに住んで荒物屋・駄菓子屋を営み、その時の経験を基に『たけくらべ』を書いたといわれています。主人公は遊女にあこがれる美登利という女の子、初めて島田に結った時の美しさは極彩色の京人形のようです。ただ、美登利も下町っ子で、男の子ともけんかするお転婆娘。
こんなに威勢の良い声は、漱石の小説、坊っちゃんの啖呵にそっくり。
短気で喧嘩っ早いのが江戸っ子気質です。なんだか「男はつらいよ」寅さんの口上にも似ていますね。
それから、震災の犠牲になった遊女を供養した吉原弁財天、酉の市で有名な鷲(おおとり)神社、江戸下町伝統工芸館では職人さんの実演を見学し、国内外の観光客で賑やかな浅草寺、仲見世、雷門まで、下町の文化を肌で感じながら、約3kmの道のりを歩き通しました。最後はみんなヘトヘトでしたが、中身の濃い見学に大満足です。浅草で食べた名物メロンパンや天丼の味は最高でした!
