人文学部ゼミブログ
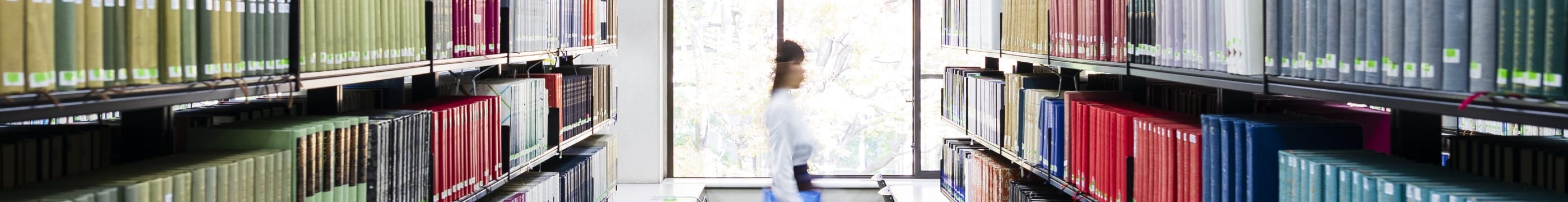
2016.02.25
- 人文学部
- 日本・東アジア文化学科
声を聴き、歴史を紡ぐ
ブログ投稿者:日本・東アジア文化学科 専任講師 村山絵美
今年度の「比較生活文化演習」では、「聞き書き」をテーマに生活文化やライフヒストリーについて学びました。前期は、「聞き書き」をもとに綴られた生活誌をテキストに用いて、明治期の農村の暮らしについて、現在の暮らしと比較しながら検討しました。後期は、6つのチームに分かれ、「聞き書き」の方法論について、関連論文や映像資料を参考にしつつ、実践を交えながら議論を重ねていきました。人のはなしを聴くということは、簡単なようでいて、実は難しいことでもあります。「聞き書き」は普段の会話とは異なるため、実践することで、さまざまな気づきがあります。事前の準備や聞き取った内容を検討するための事後調査も欠かせません。「聞き書き」に関する基礎的な理解を深めていった上で、最終的にはチームごとに語り手を探して、「聞き書き」をし、その成果を発表してもらいました。
-

写真① 最終発表会でのチーム発表 -

写真② 最終発表会の様子
今回、調査にご協力いただいた語り手の方の多くは、受講生のおじいさまやおばあさまでした。調査を通して、初めて詳しく祖父母の若い頃の経験や戦争体験について聞いたというケースが大半でした。「聞き書き」は、個人の経験に触れるだけでなく、人の経験をもとに過去と現在とのつながりを知ることができる方法であり、人や社会の奥深さを学ぶ機会でもあります。さまざまな声に耳を傾けることで、自分の知らない世界が広がっていきます。
声から紡ぐ歴史について、これからも皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
最後に、受講生のみなさんの感想の一部を紹介します。
「聞き書き調査は慣れない作業でもあったので、反省点がとても多かったですが、一人の人生の一部に寄り添うことで、教科書や政治史からは読み取れない個人の感情や視点を知ることができます。生の声で聞いた歴史なので過去の出来事だと自分と切り離したものとしてではなく、自分に引きつけて過去の生活文化を捉えることが聞き書きの魅力だと感じました。」
「今回、実際に話を聞くとき、相手の話をくみ取ろうと注意を払うこと、自分でそれを消化すること、裏づけを取れるだけとることのすべてがちゃんと自分の身になってくれそうな気がした。まだ足りないとは思うけど。それは、たぶん、「聞き書き」という調査方法が、すごく積極的で能動的な勉強の仕方だからだと思う。」
「聞き書きをすることで、消えていってしまう個人の体験や思いを形にして残すことができる。個人の体験や思いに触れることで、その人の生きた時代を知ることができるものだと感じた。聞き書きは文献を読むよりも、もっとずっと生々しく世界を広げて見ることができるものだと感じた。」
「よく話のうまさや発表のうまさに焦点が当てられますが、他人の話を聞いていると、いろいろな発見があったり、学ぶことも多くあると感じたので、普段からじっくりと誰かの話に耳を傾けてみることは、とても大切なことなのではないかと思いました。」
