人文学部ゼミブログ
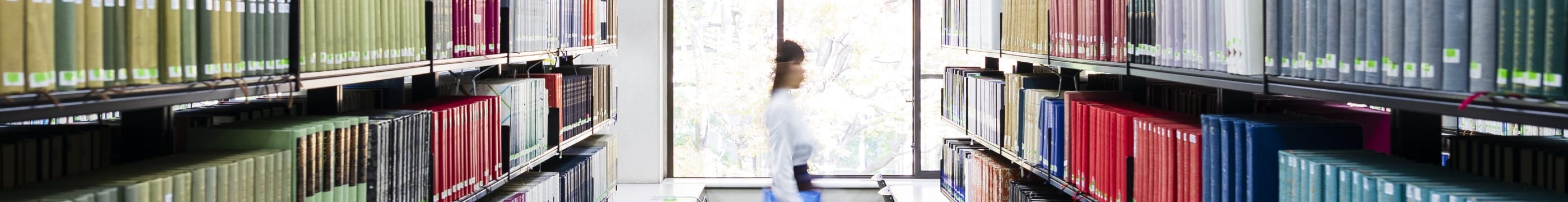
2015.10.29
- 人文学部
- 日本・東アジア文化学科
青森県霊場めぐり、ねぷた見学
ブログ投稿者:日本・東アジア文化学科 教授 福原敏男
「死ねばお山(恐山)さ行く」
死後、火葬場で焼かれて骨になって、全てが終わりですか?日本人の他界観(あの世はどこにあるのか)の一つに、日常目にする霊山の山中他界観があります。下北半島の人たちは、肉体とともに魂もなくなる、とは考えず、ご先祖の霊は毎日仰ぎ見ている山に居て、自分の霊も死んだら恐山に行くと信仰しています。

今年の福原卒業論文ゼミ+同準備ゼミでは、7月31日に恐山に出かけました。
硫黄がモウモウと湧き出る山中地獄を巡り、男性陣は自由に入れる温泉に浸かりました。恐山は、農家の人たちが農閑期に湯治を兼ねてやってくる「信仰と骨休め」が一体となった霊場なのです。山中地獄のかたわらに、宇曽利湖の極楽浜(写真1)もあります。地獄と極楽が隣り合っているのです。天国と地獄が隔絶していると考える一神教の世界では、あり得ない光景といえましょう。夏の大祭での、イタコ(巫女)が依頼者の願いに応じて死者の霊を降ろして語る口寄せが、マスコミを通じ全国的に有名です。
8月1日にはかつての城下町弘前へ。この日に弘前ネプタ行事が始まりました。青森のネブタとは趣が異なり、扇形のネプタ(灯籠)を中心とした、青森の短い夏を告げるパレードです。ネプタ以前に、弘前の代表的な祭りであった八幡宮の山車展示館にも行きました。最終日8月2日は巨大な五所川原ネプタ、岩木山の麓の岩木山神社、金木町の太宰治の生家や津軽三味線資料館なども巡りました。

写真2は金木の川倉地蔵です。女子学生のなかには、かつてこの地蔵堂の人形のそばに、早死にした子どもの霊がテレビに映った霊番組を見た人もいます。現在でも旧暦6月23・24日にはイタコによる死霊の口寄せが行われます。途中寄った久渡寺(弘前市)でも、5月のオシラ講ではイタコがオシラ祭文をかつては唱えていましたが、今は絶えました。
福原ゼミの民間信仰を巡る旅は来年も続きます。
