人文学部ゼミブログ
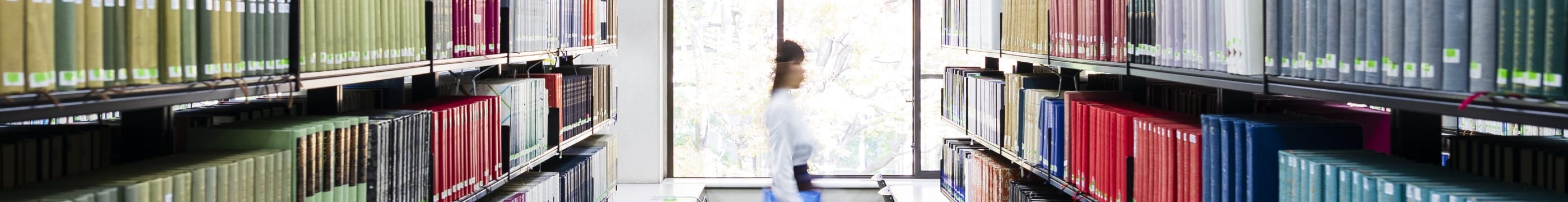
2015.03.25
- 人文学部
- 日本・東アジア文化学科
フィールドワークで実感する研究の方法
ブログ投稿者:日本・東アジア文化学科 教授 高橋一樹
現在とつながる過去のようすを知るうえで、基本的な研究の材料となるのは、古文書などの文字史料や発掘による出土遺物などですが、絵画を含む画像資料も重要な手がかりになることがあります。
私たちの日本中世史演習ゼミでは、ある武士の家に伝わった文書史料の解析をおもに進めていますが、その文書群と一緒に、1300年前後の鎌倉時代後期に作成された絵図が2点も現存しています。家・屋敷や寺社、田や畠からなる耕地、河川・水路や山林などを描いた、土地の境界争いにかかわるものです。
2枚の絵図と関連する文書史料をあわせて分析することにより、約700年前の景観を復元する研究が進められてきました。その成果と課題を自分の目でたどってみることを目的として、夏休みのゼミ合宿では、現地を実際に歩くフィールドワークを行いました。観光地でも何でもない、まったくふつうのムラを若者たちが集団で訪れるなんて、大学のゼミにおける野外調査ならではのことです。
以下の写真はそのときのもので、合宿記念の集合写真のようになっていますが、ここに写っている場所は、1枚の絵図に描かれた景観の現場であると考えられてきたところです。学生たちに囲まれた大きな石は、絵図の時代からある文化財のように扱われ、地元の教育委員会による説明板や石柱も建てられています。

しかし、新たな研究の進展によって、この場所は絵図のエリアとは異なることが明らかとなりました。現在の通説では、ここから1キロほど離れた地点に絵図の示す景観があったと理解しています。ひきつづき私たちは、そこに移動して、現地比定の根拠とされた地物を見てまわり、ひとつめの場所との異同を考え始めました。
歴史の研究は、このように身近な地域の過去をさぐることに真の醍醐味があり、さまざまな史資料を現地で得られる情報と組み合わせて読み解く作業がとても大切です。ただし、やみくもに現場を調べればよい、というわけでもありません。

