人文学部ゼミブログ
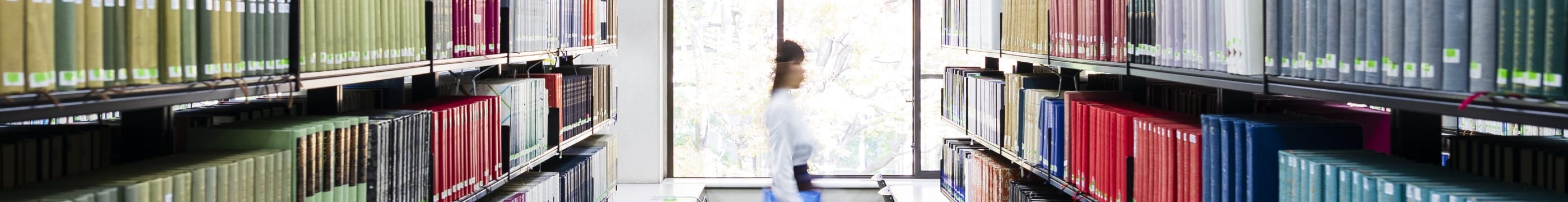
2013.07.24
- 人文学部
- 日本・東アジア文化学科
日本東アジア文化学科:史料を片手にフィールドを歩く
ブログ投稿者:日本・東アジア文化学科 教授 高橋 一樹

日本の中世にあたる平安時代の終わりから戦国時代までは、武士が支配者として確立していく時期にあたります。そうした歴史の流れに比例するように、中世の社会で作り出された文書も、武士にかかわるものが増加し、現存する中世文書のなかで、武士の家に残された例が多数派になっていきます。
武士は都と地方のいずれにも活動の足場をおき、とくに鎌倉時代以降は地方に進出する機会が増えていきました。このため、武士に関連する文書史料には、京都や鎌倉など中世の政権が所在した都市だけでなく、武士たちが所領とした地域社会に関する情報が多く含まれます。たとえば、武蔵大学のキャンパスがある練馬区の江古田(えこだ)という地名は、隣接する中野区の江古田(えごた)に淵源をもつ、といわれますが、この地名も中世の武士とのかかわりから戦国時代の史料にはじめて登場するのです。
ゼミでは、このような中世武士の子孫に伝来した古文書を読み解き、そこから教科書には載らないような地域の歴史を掘り起こしていく作業を積み重ねます。本年度前期に購読した文書群には、13世紀なかばの鎌倉に関する記述が目立ったことから、ゼミ生みんなで、史料のコピーと地図を片手に鎌倉市内の現地を歩きました。もちろん、中世の景観がそのまま残っているわけではありませんが、約800年前の史料に記述された情報を現地で体感的に理解しようとする経験は、ゼミ生たちの思考方法にも大きな刺激を与えたようです。
古文書をもちいた歴史の研究というと、なにやら大学の教室内で寡黙に取り組むイメージが強いでしょう。しかし、文書史料に登場する地域のフィールドワークを丹念に行い、現場で史料の内容を読み込むことこそが大切なのです。私たちのゼミでは、このような研究のスタイルをしっかりと実践していきたいと思います。
