人文学部ゼミブログ
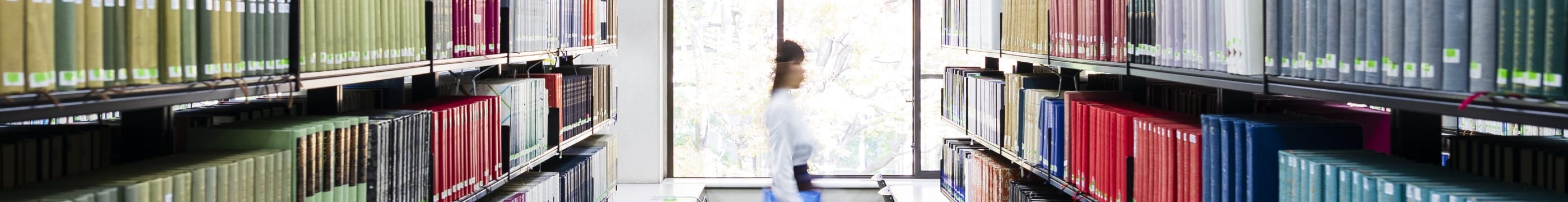
2009.04.09
- 人文学部
- 日本・東アジア文化学科
日本近代文学演習(大野淳一)
素朴な疑問、率直な印象からレポート、論文へ
この演習では毎年明治期の小説を読むことが多い。多くの作家の作品を毎回1篇のペースで とにかく多読、という年もあるし、長編1篇を1年かけて読む、という年もある。ある年の演習は、一人の作家(森鴎外)の作品を時代順に読破して行こうという、いわば両者の中間のような形を取った。やり方が一定しないのは、文学専攻の学生ばかりではないので、さまざまな関心や研究方法に対応できるようにと考えたためである。
さて、その鴎外追跡の年のある日の演習。対象としていたのは明治末の小説『青年』だった。先に発表された夏目漱石『三四郞』を意識したこの作品の主人公は、地方から上京した知的な美青年小泉純一(名前は似ているが、後に首相になった人ではない)。
彼は上京後、近所の別荘に住む銀行頭取のお嬢様、「大きい目」が印象的なお雪さんや、翻訳劇を上演中の劇場で出会った妖艶な未亡人坂井夫人などの女性と知り合い、さまざまな交流を持つ。純一はもちろん彼女たちの魅力に惹かれるのだが、なかなか恋愛に進展しない。たとえば、障子を閉め切った部屋でお雪さんと二人、寄り添って画集を見ている場面がある。お雪さんの眼は画中の人物を、純一の目はお雪さんを追う。
頬から、腮から、耳の下を頸に掛けて、障ったら、指に軽い抗抵をなして窪みそうな、鴇色の肌の見えているのと、ペエジを翻す手の一つ一つの指の節に、抉ったような窪みの附いているのとの上を、純一の不安な目は往反している。
さらに官能的なことばが続く。
袖と袖と相触れる。何やらの化粧品の香に交って、健康な女の皮膚の匂がする。どの画かを見て突然「まあ、綺麗だこと」と云って、仰山に体をゆすった拍子に、腰のあたりが衝突して、純一は鈍い、弾力のある抵抗を感じた。
しかし、純一は決してそうした官能の中に自分を解き放とうとしない。かえって「この娘を或る破砕し易い物、こわれ物、危殆なる物として、これに保護を加えなくてはならないように」感じたりするのである。
この前後をめぐって議論していた最中、ある女子学生から
「コイツ、口ばっかりじゃん!?」という発言があり、教室のあちこちから共感の笑い声が揚がった。確かに、それは印象としてはなかなか鋭い。Aを通り越してSと評価しても良いくらいである。
しかし、「××じゃん!?」という印象のままでは論文にはならない。
「じゃあ、『小泉純一は、なぜ口ばっかりなのか?』なら、アリですか?」
解くべき問題を明確に示せた、という意味で、「アリ」。しかし、「口ばっかり」というのは論文の文体ではないだろう(「アリ」もだが)。
「じゃあ、『なぜ、行動が伴わないのか?』では?」
アリ! いや、良し! しかしその前に、「どのように『口ばっかり』なのか」を確認することが必要だろう。
そこからは百花斉放。
「こいつ、知識は凄くてやたら外人の名前を並べて恋愛論をやるんだよね」
「そうそう、『欧米か!?』ッて、突っ込みたいくらい」
「それに、女には娼婦型と母親型しかない、なんて生意気な事もいうし」
「それって、彼の友だちがする話でしょ?」「あ、そうだっけ?」
「でも、美人の坂井夫人とは『口ばっかり』の関係ではないみたいだよ。彼女の家を訪ねた後、『知る人』になったって書いてある」
「そうだけれど、これは『衝動』で『恋愛』ではないッて何度も断ってるね」
「純愛派なのかな?」
どれもおもしろい指摘だ。これは宿題だけれど、千年前に『源氏物語』なんていう性愛派?の傑作を生んだ日本で、何で今頃「純愛派」が出て来るのか。
「大勢出て来た、あの外人たちの思想の影響ですか?」
そう! いや、それも宿題。
「先生、鴎外の主人公って、みんなこうですか?」
高校の国語で『舞姫』をやった人も多いはずだが。
「あ、あれは一目惚れです! 初めて会った時、エリスの青い瞳が豊太郎のハートを直撃するんです!」……
この後議論はまたあちこちに飛び火したが、本欄での紹介はここまでにしよう。「口ばっかり」から始まって、西洋思想の問題、文学史の問題、鴎外作品の問題などが芋蔓式に掘り起こされたのだった。
ともかく、初めて読んで感じた印象や疑問、それを「率直」や「素朴」なままにしておかないで明確な問の形に成長させて行くことが重要である。そのためには……、という例としてこの演習での体験を書いてみた。実際鴎外と近代の恋愛観をテーマとした、優秀な卒論を書いた先輩もいる。後に続く皆さんにもがんばってもらいたい。
もう一つ、注文。上の例は演習だから、大勢で討論する中で議論が深まって行った。しかし、まずは自分の頭の中で自問自答して欲しい。論文ではそれが大事、と言うより、演習でもそれをやった上での発表・討論となれば、さらに深い認識に到達できるだろう。
では、後は教室で。
この演習では毎年明治期の小説を読むことが多い。多くの作家の作品を毎回1篇のペースで とにかく多読、という年もあるし、長編1篇を1年かけて読む、という年もある。ある年の演習は、一人の作家(森鴎外)の作品を時代順に読破して行こうという、いわば両者の中間のような形を取った。やり方が一定しないのは、文学専攻の学生ばかりではないので、さまざまな関心や研究方法に対応できるようにと考えたためである。
さて、その鴎外追跡の年のある日の演習。対象としていたのは明治末の小説『青年』だった。先に発表された夏目漱石『三四郞』を意識したこの作品の主人公は、地方から上京した知的な美青年小泉純一(名前は似ているが、後に首相になった人ではない)。
彼は上京後、近所の別荘に住む銀行頭取のお嬢様、「大きい目」が印象的なお雪さんや、翻訳劇を上演中の劇場で出会った妖艶な未亡人坂井夫人などの女性と知り合い、さまざまな交流を持つ。純一はもちろん彼女たちの魅力に惹かれるのだが、なかなか恋愛に進展しない。たとえば、障子を閉め切った部屋でお雪さんと二人、寄り添って画集を見ている場面がある。お雪さんの眼は画中の人物を、純一の目はお雪さんを追う。
頬から、腮から、耳の下を頸に掛けて、障ったら、指に軽い抗抵をなして窪みそうな、鴇色の肌の見えているのと、ペエジを翻す手の一つ一つの指の節に、抉ったような窪みの附いているのとの上を、純一の不安な目は往反している。
さらに官能的なことばが続く。
袖と袖と相触れる。何やらの化粧品の香に交って、健康な女の皮膚の匂がする。どの画かを見て突然「まあ、綺麗だこと」と云って、仰山に体をゆすった拍子に、腰のあたりが衝突して、純一は鈍い、弾力のある抵抗を感じた。
しかし、純一は決してそうした官能の中に自分を解き放とうとしない。かえって「この娘を或る破砕し易い物、こわれ物、危殆なる物として、これに保護を加えなくてはならないように」感じたりするのである。
この前後をめぐって議論していた最中、ある女子学生から
「コイツ、口ばっかりじゃん!?」という発言があり、教室のあちこちから共感の笑い声が揚がった。確かに、それは印象としてはなかなか鋭い。Aを通り越してSと評価しても良いくらいである。
しかし、「××じゃん!?」という印象のままでは論文にはならない。
「じゃあ、『小泉純一は、なぜ口ばっかりなのか?』なら、アリですか?」
解くべき問題を明確に示せた、という意味で、「アリ」。しかし、「口ばっかり」というのは論文の文体ではないだろう(「アリ」もだが)。
「じゃあ、『なぜ、行動が伴わないのか?』では?」
アリ! いや、良し! しかしその前に、「どのように『口ばっかり』なのか」を確認することが必要だろう。
そこからは百花斉放。
「こいつ、知識は凄くてやたら外人の名前を並べて恋愛論をやるんだよね」
「そうそう、『欧米か!?』ッて、突っ込みたいくらい」
「それに、女には娼婦型と母親型しかない、なんて生意気な事もいうし」
「それって、彼の友だちがする話でしょ?」「あ、そうだっけ?」
「でも、美人の坂井夫人とは『口ばっかり』の関係ではないみたいだよ。彼女の家を訪ねた後、『知る人』になったって書いてある」
「そうだけれど、これは『衝動』で『恋愛』ではないッて何度も断ってるね」
「純愛派なのかな?」
どれもおもしろい指摘だ。これは宿題だけれど、千年前に『源氏物語』なんていう性愛派?の傑作を生んだ日本で、何で今頃「純愛派」が出て来るのか。
「大勢出て来た、あの外人たちの思想の影響ですか?」
そう! いや、それも宿題。
「先生、鴎外の主人公って、みんなこうですか?」
高校の国語で『舞姫』をやった人も多いはずだが。
「あ、あれは一目惚れです! 初めて会った時、エリスの青い瞳が豊太郎のハートを直撃するんです!」……
この後議論はまたあちこちに飛び火したが、本欄での紹介はここまでにしよう。「口ばっかり」から始まって、西洋思想の問題、文学史の問題、鴎外作品の問題などが芋蔓式に掘り起こされたのだった。
ともかく、初めて読んで感じた印象や疑問、それを「率直」や「素朴」なままにしておかないで明確な問の形に成長させて行くことが重要である。そのためには……、という例としてこの演習での体験を書いてみた。実際鴎外と近代の恋愛観をテーマとした、優秀な卒論を書いた先輩もいる。後に続く皆さんにもがんばってもらいたい。
もう一つ、注文。上の例は演習だから、大勢で討論する中で議論が深まって行った。しかし、まずは自分の頭の中で自問自答して欲しい。論文ではそれが大事、と言うより、演習でもそれをやった上での発表・討論となれば、さらに深い認識に到達できるだろう。
では、後は教室で。
