人文学部ゼミブログ
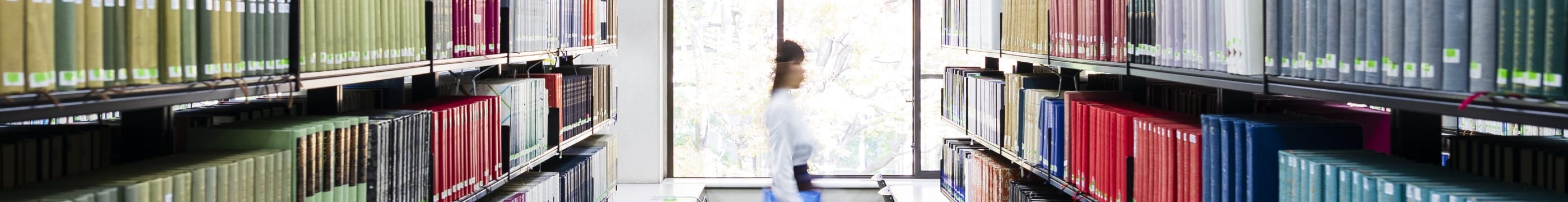
2008.01.22
- 人文学部
- ヨーロッパ文化学科
ヨーロッパ史演習1・2(踊 共二)
広域ヨーロッパ文化コースの歴史系のゼミを担当しています。このコースは“国境”や“言葉の違い”を超えてヨーロッパ諸地域に広く共有されてきた文化現象 を扱うところに特徴があります。学生たちが行う研究自体は特定の地域や時代に焦点をあてたものですが、それらを口頭発表し、互いに知識を分かち合う過程で、同じ問題を違った角度から見ていたことに気づくこともしばしばです。ドイツのことを学んでいる人も、フランスのことを学んでいる人も、イタリアや北欧のことを学んでいる人もいます。2007年度後期の学生たちの口頭発表のテーマの一部をあげておきます(これらはレポートのテーマでもあります)。ところで、過ぎ去った時代の諸現象をしっかり調べる仕事は、じつは“現代”をよりよく知ることにつながります。何事にも、隠れた地下水脈のような、深くて長い歴 史があるからです。下記の研究テーマはいずれも、まさに現代的視点で歴史研究を行った好例だと思います。みなさんも仲間に加わりませんか。
中世ヨーロッパの家屋:‘かまど’と‘煙突’の文化史
ヨーロッパの城塞と宮殿:辺境の軍事施設から都市の王宮へ
色彩にみる中世ヨーロッパ:‘愛’と“哀しみ”を語る色
中世・ルネサンスの服飾文化:‘ざくろ’模様をめぐって
中世の放浪芸人:ストリート・パフォーマンスに生きる人々
愛の手紙:アベラールとエロイーズの場合
“水車”のある風景:中世人の日常生活
疫病の克服:黒死病とコレラの時代
“死”と“埋葬”の考古学:ヨーロッパ人の死にかた
中世人の“遺言状”:イタリア都市の場合
ヨーロッパの深い森:宗教と経済活動
“捨て子”たちの中世史:フィレンツェの事例
中世ヨーロッパの彩色写本:『ベリー公のいとも豪華なる時祷書』を中心に
中世ヨーロッパにおける結婚と家族
ナイフとフォークとスプーン:その誕生と普及の歴史
※ヨーロッパの民間伝承:16世紀中央スイスの事例
最後のものは、教員(わたし)が行った報告です。この報告ではスイス中央部の山地、ピラトゥス山とリギ山に残る「不死の乙女」や「森のこびと」「竜(の石)」「鬼火」「闇夜を行く死者の軍勢」「ポンテオ・ピラトの亡霊」などの神話と伝説を紹介しました(16世紀のとても古い記録から再現。現地取材もしてきました)。この内容は2007年12月に東京大学(駒場キャンパス)で学外の教授たちや学生さんたちと行った研究会でも発表しました。来年は「放浪者」 (旅芸人や遍歴の学徒)、「占い師」、「魔女」などの記録を掘り起こして紹介したいと思っています。資料紹介の論文も書くつもりです(なにせ500年前の記録ですから解読に時間がかかりますが)。
中世ヨーロッパの家屋:‘かまど’と‘煙突’の文化史
ヨーロッパの城塞と宮殿:辺境の軍事施設から都市の王宮へ
色彩にみる中世ヨーロッパ:‘愛’と“哀しみ”を語る色
中世・ルネサンスの服飾文化:‘ざくろ’模様をめぐって
中世の放浪芸人:ストリート・パフォーマンスに生きる人々
愛の手紙:アベラールとエロイーズの場合
“水車”のある風景:中世人の日常生活
疫病の克服:黒死病とコレラの時代
“死”と“埋葬”の考古学:ヨーロッパ人の死にかた
中世人の“遺言状”:イタリア都市の場合
ヨーロッパの深い森:宗教と経済活動
“捨て子”たちの中世史:フィレンツェの事例
中世ヨーロッパの彩色写本:『ベリー公のいとも豪華なる時祷書』を中心に
中世ヨーロッパにおける結婚と家族
ナイフとフォークとスプーン:その誕生と普及の歴史
※ヨーロッパの民間伝承:16世紀中央スイスの事例
最後のものは、教員(わたし)が行った報告です。この報告ではスイス中央部の山地、ピラトゥス山とリギ山に残る「不死の乙女」や「森のこびと」「竜(の石)」「鬼火」「闇夜を行く死者の軍勢」「ポンテオ・ピラトの亡霊」などの神話と伝説を紹介しました(16世紀のとても古い記録から再現。現地取材もしてきました)。この内容は2007年12月に東京大学(駒場キャンパス)で学外の教授たちや学生さんたちと行った研究会でも発表しました。来年は「放浪者」 (旅芸人や遍歴の学徒)、「占い師」、「魔女」などの記録を掘り起こして紹介したいと思っています。資料紹介の論文も書くつもりです(なにせ500年前の記録ですから解読に時間がかかりますが)。
