人文学部ゼミブログ
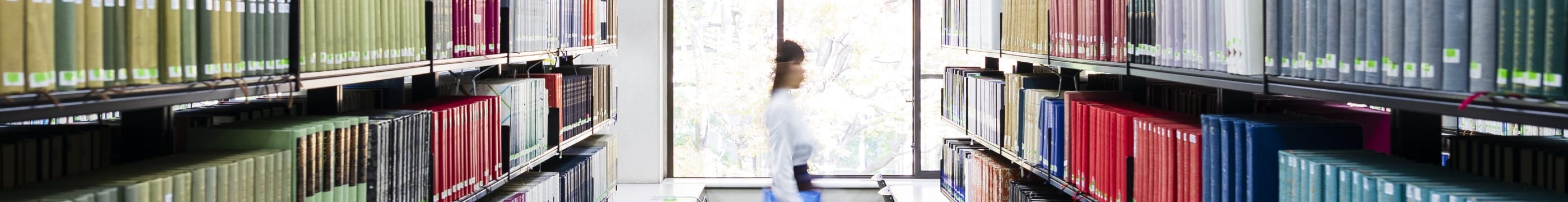
2008.01.15
- 人文学部
- ヨーロッパ文化学科
中・近世ドイツ語演習、中・近世ドイツ文学演習 (新田春夫)
このゼミでは中世から近世にかけてのドイツ語とそれによって書かれたドイツの文芸を扱っています。
ヨーロッパ中世社会は国王や教皇を頂点とした封建社会であり、その文化の主要な担い手は王侯貴族です。ですから、文芸作品の作者はだいたい騎士、または、聖職者です。

ドイツ中世の文芸作品には叙事詩と抒情詩があります。叙事詩は騎士が活躍する物語で、例えば、『ニーベルンゲンの歌』や『トリスタンとイゾルデ』などがあ ります。これらの作品はワーグナーのオペラなどになっていますから、きっと名前は聞いたことがあると思います。『ニーベルンゲンの歌』はゲルマン伝説とし て伝承されたものです。また、『トリスタンとイゾルデ』はイギリスとのアーサー王伝説のひとつですが、これはケルト伝説にその起源があります。このように 中世ヨーロッパの文芸はしばしばヨーロッパの先住民族であるケルト人やゲルマン人に由来し、ドイツ、フランス、イギリスなどの各国の文芸の素材となってい ます。また、抒情詩は宮廷恋愛歌で、ドイツではミンネザングと言われるものです。これもスペインやフランスの宮廷から伝わってきたものと言われています。 このようにドイツの言語や文芸と言ってもヨーロッパ全体の歴史と文化に深く関わっています。
このゼミでは最初に簡単に中世ドイツ語を学 んだ上で、それらの文芸作品をオリジナルで読みます。なぜなら、中世では文書や本は羊皮紙に書かれていて、非常に高価なもので、一部の裕福な人しか持っていませんでした。また、文字を読める人も限られていました。ですから、これらの文芸作品は王侯貴族などが集まった宮廷で朗読されたのです。さらに、これら の文芸作品は耳で聞いてわかりやすく、また、記憶にとどめやすいように、一定の形式とリズムがあり、韻を踏んでいます。朗読するというよりは楽器の伴奏が ついて、メロディにのせて歌うように語ったのです。このように、中世の文芸作品を本当に鑑賞するためには現代語に訳したものよりはオリジナルで読むのがいいのです。
近世になるとそれまでのキリスト教と王侯貴族の封建社会から市民階層が主人公である国民国家への移行が始まります。それまでのカトリックに反対して、ルターによる宗教改革が行われ、正典であったラテン語聖書に対してルターは一般の人が読めるように、ヘブライ語、ギリシア語の原典からドイツ語へ翻訳をします。また、キリスト教の支配から脱却して、ローマ・ギリシアの文化を再評価するルネサンスと言われる人文主義が興ります。そのことからイソップ物語、ホメロスのイーリアスやオデュセイアなどがドイツ語に翻訳されます。そしてこれら はちょうどその頃に開発された紙と手書きよりははるかに手間と費用がかからない印刷術によって文書や本が安価に大量に製作することができるようになったために広く読まれるようになりました。
このゼミでは、その書き手が市民であり、また、文章は散文で書かれていて、朗読ではなく主に黙読 し、内容的にはきわめて実用的であり、それまでの支配者である王侯貴族、聖職者たちに対抗し、新しい市民社会を築こうとする庶民の心意気が満ち溢れ、しばしば過激な調子の近世のオリジナル・テクストも読んで中世との対比をします。
