経済学部ゼミブログ

2020.06.03
- 経済学部
- 経営学科
オンラインのゼミでのグループワーク
ブログ投稿者:教授 竹内広宜
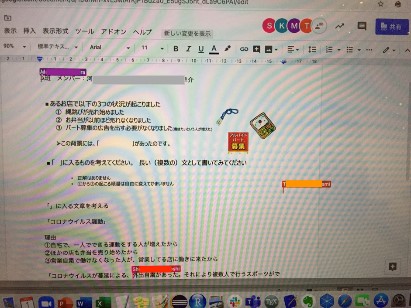
2020年度前期の授業は、新型コロナウィルスの影響により、オンラインで実施されています。私たち教員は、授業内容や履修者の数を考え、様々な形式でオンライン授業を行なっています。授業開始から1ヶ月、私が慣れないツールに右往左往している一方で、学生の皆さんがPCやスマートフォンを使って様々なスタイルの授業に順応している様子を見ると、素晴らしく、そして羨ましくも感じます。
私の専門は先進情報通信技術(流行りの人工知能:AIも含みます)の活用ですが、ゼミでは、あまり細かい技術の詳細にとらわれず、様々なテーマについて、特に答えが自明でない課題を設定してグループ活動を行なっています。特に専門ゼミナール 1・2部(2年生ゼミ・3年生ゼミ)では、技術に関する新しいモノやコトを実際に触れながら、感じたことや考えたことをグループ内で共有してまとめるという活動を行なっています。このようなグループワークでは、フリップチャートと呼ばれる大きな紙に、アイディアを書いた付箋を貼って議論を可視化することが、重要な活動の1つです。このような、対面で物理的に交流することを前提としたグループワークは、オンラインゼミへの移行により難しくなります。方向転換なり工夫が必要です。
まずZoomと呼ばれるオンライン会議ツールを使ってゼミを始めてみると色々な発見がありました。例えば、このツールには会議室を複数に分けて個別グループで議論する機能(ブレークアウトルーム)があるのですが、ゼミメンバーはいきなりグループに分けられても物理的に同じ空間にいる感覚がないため、話をするきっかけがつかめず沈黙が続くことがあるようです。1年以上一緒に活動してきた3年生のゼミでも、そのような意見が出てびっくりしました。そこで、毎回のグループワークで、「一度カメラをONにしてみよう」や「今日のお題(例えば、昼ごはんは何?) について各自しゃべる」というルーティンを取り入れて試しています。
また、コミュニケーションを活性化させる工夫だけでなく、グループでの活動した成果を出力する方法も検討課題です。最初に導入したのは、Webブラウザー上で同時に編集できる文書ソフト(Office Online, Googleドキュメントなど)の利用です。Google ドキュメントを使い、課題に対してグループで考えながら一つの回答を文章として書いている様子が写真1です。ブレークアウトルームに私も参加し、そのグループが編集している様子を見せてもらいました。お互いしゃべりながら、記述を修正・加筆しながら課題を進めている様子が見て取れました。誰が文書中のどこを編集しているかがわかるので、「サボって見ているだけ」は難しいようです。
-
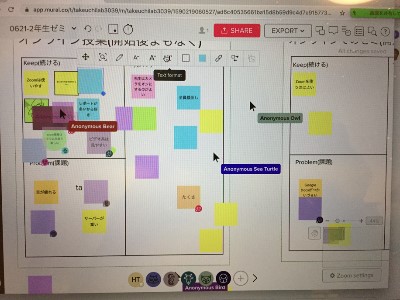
写真2:Digital Mural上で各自が意見の付箋を貼っている様子 -

写真3:付箋のアイディアに対して投票した結果(赤い丸の数が投票数)
オンラインでのゼミ活動を進めていく中で、「オンラインで活動した後、対面で会ったら、どんな感じになるのだろう?」というコメントがありました。対面形式でのゼミ活動が始まった時、新たな化学反応が起きる予感がします。今から楽しみです。
