NEWS & EVENTS
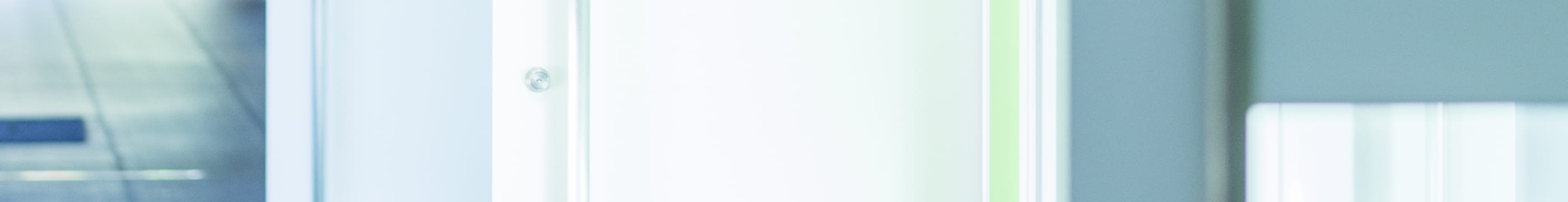
2019.05.16
- 教育・研究
- 人文学部
- 広報室
お知らせ
日本・東アジア文化学科 小川栄一 教授 著『漱石を聴く コミュニケーションの視点から』が刊行されました
本書の概要

夏目漱石の小説作品をコミュニケーションの観点から分析した本です。
漱石の「F+f」理論に基づくコミュニケーションが、初期には笑いやユーモアの表現、後期には人間対立や人間不信など近代人の懊悩の表現に用いられたことを明らかにしています。
漱石の東京訛り、うそや翻弄の会話、演説なども考察しています。
漱石の「F+f」理論に基づくコミュニケーションが、初期には笑いやユーモアの表現、後期には人間対立や人間不信など近代人の懊悩の表現に用いられたことを明らかにしています。
漱石の東京訛り、うそや翻弄の会話、演説なども考察しています。
著者より一言
近代におけるコミュニケーション研究の資料として漱石の小説作品に大きな可能性を見出しました。漱石作品は日本語の談話資料として着目に値します。その小説にはさまざまなタイプの会話が展開されていますが、実に生き生きとしたことば遣いが感じ取れます。それを当時の音調にふさわしく朗読してみれば、当時の溌剌とした日本人の声が響いてきます。漱石は山の手ことばと下町ことばに精通していました。作品中にしばしば現れる下町ことばからは江戸っ子の心意気までも伝わってくるかのようです。各章扉に会話の一節を抜き書きしたのも、その音調を読者に実感していただきたいからです。それも黙読でなく、ぜひ音読してください。会話の音調も漱石作品の魅力の一つといえます。本書は、このような味読を通じて、漱石が『文学論』で展開した「F(認識)+f(情緒)」理論をコミュニケーションの視点から明らかにしながら、漱石・作品像を立体化する試みです。(小川栄一)
ぜひ、ご一読ください。
ぜひ、ご一読ください。
